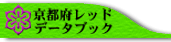| 選定理由 |
産地が極限され個体数も少ないが、局地的には安定している。 |
| 分布 |
北海道から九州、朝鮮半島。
◎府内の分布区域
中部地域。 |
| 存在に対する脅威 |
森林伐採、空中湿度の低下。 |
| 必要な保全対策 |
深山の岸壁に着生する希少種で、移植は困難。湿度が低下すると、容易に消失する。イタチシダ類では珍しく有性生殖をし、学術的に貴重。 |
| 形態 |
常緑の多年草。通常川沿いの岸壁などに着生する。葉は卵形から狭卵形、厚い紙質、2回深裂から3回中裂。葉軸の鱗片は黒〜黒褐色で、開出または反転気味につく。
◎近似種との区別
ヤマイタチシダ、オオイタチシダ、イヌイワイタチシダなどは、葉軸の鱗片が圧着気味につくから、区別はやさしい。
◎参照 原色日本羊歯植物図鑑;pl.36-206,101頁(1959),京都府草木誌;9頁(1962),しだの図鑑;168頁(1986),日本の野生植物 シダ;pl.125-1〜2,198頁(1999),改訂・近畿地方の保護上重要な植物;(No.5084、準)(2001) |