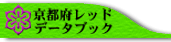| 選定理由 |
府内では自生地が非常に限られており、個体数も少なく絶滅が危惧される。 |
| 形態 |
直立する落葉小高木で、つるにならない。葉は披針状長楕円形、鋭尖頭で、基部はわずかに不相称、全縁で、薄い紙質。葉の表面は粉白色を帯びる。花序は短い柄のある小さな集散花序で、枝の上部の葉腋にでる。花期は6月。花は小さく黄色。果実は狭長楕円形、長さ7〜8mm、黄色から赤色を経て暗赤色となる。
◎近似種との区別
近縁のBerchemia(クマヤナギ属)では多くがつる性で、托葉は合着するのに対して、本属は直立性で托葉は離生する。
◎参照 日本の野生植物木本II:57頁,原色日本植物図鑑木本I:No.303 |
| 分布 |
本州、四国、九州、朝鮮半島(南部)、中国大陸。
◎府内の分布区域
北部地域(中丹地域)、南部地域(山城中部地域)。 |
| 生存に関する脅威 |
森林伐採、土地造成、道路工事などが減少の主要因である。 |
| 必要な保全対策 |
森林を伐採する際には詳細な樹木調査が必要である。 |