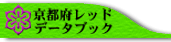| 選定理由 |
北半球の高緯度地方に広く分布し、日本では中部地方や東北地方の高山帯に分布しているが、京都市のような低地に生育しているのは極めて稀なことである。 |
| 形態 |
植物体は赤褐色で、2mm程度という極めて微小なコケで、密により集まって小さなコロニーを形成する。葉は茎に横につき、ほぼ円形で1/2ぐらいまで2裂し、裂片は三角形状で全縁、先端は尖る。葉細胞は一様に肥厚し、トリゴンは小さい。腹葉はない。非常に頻繁に花被をつける。
◎近似種との区別
他の種からは、葉が深く切れ込まず、裂片が幅広い三角形状で、葉細胞が一様に肥厚することによって区別される。 |
| 分布 |
本州(中部地方と東北地方の高山、京都府):北米、ヨーロッパ。
◎府内の分布区域
京都市深泥池。 |
| 生態的特性 |
高山帯の土上や腐植上に密に寄り集まって、小さなコロニーを形成する。 |
| 現状・脅威・対策 |
深泥池の浮島上のビュルテの上にたまった腐植上に小さなコロニーを形成する。浮島の遷移の進行に伴う一層の陸地化に注意し、遷移が人為的な要因によって急速に進行しないように配慮する。 |