南丹広域振興局
ここから本文です。
おいしい黒大豆を食べよう!

みなさんは大豆はお好きでしょうか。
大粒でふっくらもっちりとした味わいが特徴の黒大豆には、アントシアニンというポリフェノールが含まれています。スイーツや黒豆とうふなど、様々な形で楽しめるのも魅力的ですね。
今回は、そんな黒大豆をご紹介したいと思います。
丹波黒大豆とは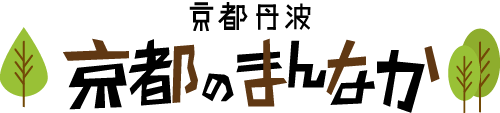

黒大豆とは“畑の肉”と言われる白(黄)大豆、青大豆、赤大豆など多くの大豆の種類の中の1つで表皮の色が黒色の大豆のことです。
かつて「丹波国」と呼ばれた現在の京都府と兵庫県にまたがる丹波地方は、昔から黒大豆が地域の特産として作られてきました。その黒色大粒の在来種を、「丹波黒大豆」と呼び、この地域以外で生産される黒豆と区別されています。
「丹波黒大豆」がいつごろ成立したかは定かではありませんが、倭名類聚抄(935年)に当時の食品として「烏豆(クロマメ)」として大豆と区別され、16世紀には宮中への献上物に「黒豆」の名があることから、このころにはすでに栽培は盛んであったと考えられています。
黒豆と言えばお正月のお節料理に欠かせない食材ですが、お節料理に黒豆を食べ出したのは室町時代に砂糖がないためこんにゃくと炊き合わせて「座禅豆」と呼ばれ食べられていたものが起源と言われています。
江戸時代中期までの日本の食文化や日本古来の食慣習の多くは、京都を中心とした宮中に起源があり、京都宮中の近隣に位置した丹波国を中心に栽培されていた黒豆が宮中へ贈られお正月に食べられていたものが、その後日本の食文化として各地へ広がって行ったとも考えられております。

京都府産黒大豆「新丹波黒」
京都府において大豆栽培の研究が始まったのは昭和6年で、当時の供試品種に丹波黒大豆の名が記載されています。
この頃既に農会経営の採種圃でとれた黒大豆種子が市町村を経て農家に配布されており(昭和7年府農会報)、収量は当時の記録から反1石(120~130kg)程度となっています。昭和10年代後半から40年代前半は、ほとんど試験研究が行われておらず、この間自家採種によって栽培は続けられていましたが、品種がばらつき安定した良質生産が得られない状態となっていました。

昭和46年に第一次水田再編対策として、黒大豆が転換畑への主たる導入品目とされ、京都府民業試験場において栽培試験が始まり、丹波各地より17系統が採種され優良種の選抜が行われたのです。昭和50年から3年間、総合助成「丹波黒大豆の良質生産技術確立に関する試験」が実施され、耕種基準や産地特性等が明らかにされるとともに、地元丹波町の農家が所持する種子から優良種3系統が選出され京都1号、2号、3号と名付けられました。その中で京都1号は品種、収量とも他の2系統より優れていたことから、本系統の種子を府・町・農協によって丹波地域へ広く配布されることとなったのです。
昭和56年にこの京都1号が奨励品種として「新丹波黒」と命名され、府の代表的段産物に位置づけされ水田農業確立対策の重点作物として振興が図られました。
現在は基準価格が保障された商品価値の高い安定作物として地域に定着しています。
「新丹波黒」の特徴

京都の黒豆・新丹波黒は大粒でシワがなく、煮炊きしても形崩れしないのが特徴です。
都々逸にも「丹波の丹波黒は色は黒でも味が良い」とうたわれ、古くからその美味しさが全国に浸透していました。
夏の昼夜の温度差と、秋の霧が黒豆を大きくゆっくり熟成させているのではないかともいわれています。
味、品質、大きさとも日本一といわれる新丹波黒大豆はカルシウムやビタミン、蛋白質を多く含む言わずもがなの健康食品です。
黒大豆は100粒の重さが40gほどで大粒大豆といわれますが、新丹波黒は85~90gもある極大粒品種です。
また、この品種は、別名「粉吹き大豆」といわれるように、種皮の表面に白い粉が浮き出し、粉が多いほど高級品として扱われます。
販売時期は12月~1月。おせち料理のひとつとして欠かすことの出来ない黒豆の甘煮には「今年もまめに暮らせますように」と、健康・長寿の願いが込められています。
その他にも、黒豆ご飯、蒸しパン、甘納豆など、いろいろな楽しみ方があります。
非常に大粒で食べ応えのある新丹波黒を、是非ともみなさんで食べてみてくださいね。

お問い合わせ
南丹広域振興局地域連携・振興部 企画・連携推進課
亀岡市荒塚町1-4-1
電話番号:0771-24-8430
ファックス:0771-24-4683