南丹広域振興局
ここから本文です。
おいしいしめじを食べよう!絶品大黒本しめじをご紹介

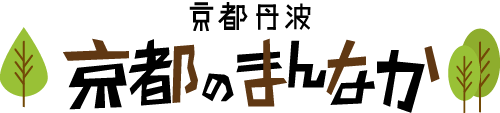 おいしい大黒本しめじを食べよう!
おいしい大黒本しめじを食べよう!
みなさんは「大黒本しめじ」というしめじをスーパーや道の駅で見かけたことはありますか?
大黒本しめじは、その希少性から「幻のきのこ」とも呼ばれています。
20年程前に人工栽培に成功し、三重県を中心に栽培されてきましたが、最近では京都丹波地域で栽培が行われています。
今回は、この「大黒本しめじ」をご紹介したいと思います!
大黒本しめじとは

大黒本しめじは、水と緑の綺麗な町、京丹波町で育てられています。
京丹波町は、丹波松茸・丹波黒豆・丹波栗・瑞穂大納言小豆等の山の幸、里の幸の産地としても有名です。
「大黒本しめじ」は、京丹波町内にある瑞穂農林株式会社で栽培されている「ホンシメジ」というきのこの商品名です。
2001年に設立されたこちらでは、京都府内で発生する間伐材を利用して「ハタケシメジ」(大粒丹波しめじ)の生産をしていましたが、2013年に大黒本しめじの生産を開始しました。
現在では、日本最大のシェアを誇る大規模栽培を実現しています。
大黒本しめじは、今まであまり市場に出回っていませんでしたが、最近はいろいろなお店で見かけるようになりました。栽培が非常に難しいことで知られておりとても希少なきのこであることから、「幻のきのこ」と呼ばれています。
ブナシメジの栽培期間は約100日ですが、大黒本しめじは約1.3倍の約130日かかります。
さらに、カビや細菌に弱いため、長い期間キレイな環境で育てる必要があり、栽培開始後~30日間は特殊な培養室で栽培する必要があります。
大黒本しめじを育てる菌床には、間伐材を活用した杉のおが粉を使用しています。森の資源を有効利用しているんですね。
このように、徹底的な衛生管理のおかげで安定した生産が可能となっています。

大黒本しめじの特徴をご紹介

通常のしめじよりもプリっと大きく、コリコリとした食感が特徴の大黒本しめじ。
松茸を圧倒する程の旨み成分が含まれており、口に含むと、ほのかに「木」の香りがします。
旨み成分が豊富で歯ごたえたっぷりな大黒本しめじは、そのままの味を生かして塩焼きもおいしいですし、和洋中問わず煮物・焼き物・汁物をはじめ、いろいろな料理にアレンジしても美味しいです。
その優れた品質により「京のブランド産品」としても認定されています。
たくさんのレシピに利用できる大黒本しめじを是非とも食べて見て下さいね!
お問い合わせ
南丹広域振興局地域連携・振興部 企画・連携推進課
亀岡市荒塚町1-4-1
電話番号:0771-24-8430
ファックス:0771-24-4683