南丹広域振興局
ここから本文です。
伝統芸能に触れよう~和知人形浄瑠璃~

みなさんは普段から伝統芸能に触れられる機会はありますか?
伝統芸能とは、日本に古くから伝えられてきた能楽、人形浄瑠璃、歌舞伎などの演劇や音楽などのことをいいます。
今回は、そんな伝統芸能のひとつである和知人形浄瑠璃についてご紹介したいと思います。
和知人形浄瑠璃とは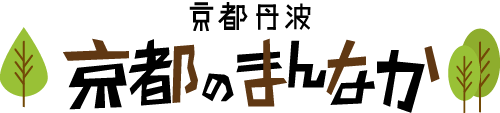


和知人形浄瑠璃とは、京丹波町の和知地域で行われる人形浄瑠璃です。
人形浄瑠璃とは、義太夫節の浄瑠璃を三味線で語るのに合わせて人形を操る演劇で、日本の伝統芸能の一つとして知られています。
和知地域は、黒豆や栗で有名な京丹波町の北部に位置する農業や林業のまちであり、かつては京都と山陰を結ぶ街道の宿場町として栄えていました。
昔から伝統芸能が盛んであり、和知太鼓・人形浄瑠璃・文七踊り・小畑万歳は「和知4大芸能」と呼ばれ、親しまれてきました。
なかでも和知人形浄瑠璃は、150年以上の歴史を持ち、現在も町内にある道の駅「和」に併設されている伝統芸能常設館で定期公演が開催されるなど、地元の誇りとして定着しています。
歴史ある伝統芸能を、一度は見てみたいと思いませんか?
和知人形浄瑠璃の魅力

浄瑠璃(三味線と語り)に合わせて人形を操る人形浄瑠璃は、一般的には1体の人形を3人の人間が操りますが、和知人形浄瑠璃は人形1体をたったひとりで扱います。
しかも、人形は大振りですので、全国でも珍しい形態となっています。当然のことながら難易度は格段に高くなるので動きへの制約も生まれてしまいます。しかし、すべて一人の人間の感性で手足や顔(目)を動かすことによって織りなされるので、1体の人形を3人で操る人形浄瑠璃と比較すると、格段に統一感が向上します!それに伴い、感情表現のリアリティが高まるという利点もあるのです。
現在、浄瑠璃会のメンバーは14名で構成されていて、内訳は三味線が2名・語りが4名・人形遣いが8名となっています。上演が可能な演目は8題目あり、うちひとつは30年前に誕生した和知オリジナル(長老越節義之誉)となっています。通常30分ほどのものが多いなかでこの作品は1時間半にも及ぶ大作となっていて、今でも高い人気を誇っています。
人形浄瑠璃の人形

人形浄瑠璃における人形は、いわば「舞台役者」。
この人形の大きな魅力のひとつは、頭(かしら)にあります。和知人形浄瑠璃では、50体ほど保管されている人形は、阿波人形の名工・天狗屋久吉の手によるものも多く、精巧な造りと美しさはまさに芸術品。目と口、眉などが動く仕掛けになっており、鯨の髭で作られた糸を巧みに操り、喜怒哀楽の感情表現を作り出します。
伝統芸能の継承

伝統芸能において、昔から守り伝えられてきた形のない「わざ」を次世代に引き継ぐためには、この「わざ」を持っている人(後継者)を育てる必要があります。
和知人形浄瑠璃にも同じことが言え、江戸時代末期、農家の閑散期に嗜んだ「人形回し」が、明治初期には芸団が結成されるほどになり、さらに大阪の文楽に携わった熟練者が加わり発展を遂げてきました。その後、まちの過疎化が進行するなかで、その継承のために若い世代に興味を持ってもらおうと、和知地域の小中学校では正規の授業の中に人形浄瑠璃が取り入れられています。
実際に、定期公演に参加できるレベルに上達する生徒も現れ、後継者不足の悩みにも一筋の光が見えはじめました。
これからも、学校の授業をきっかけとしてどんどん若い人たちが興味を持ってくれることを願っています。
定期公演
「京丹波 伝統芸能 文化サークル」(和知人形浄瑠璃のほか多数出演)
日時:毎月第四土曜日(8月、12月を除く)午後1時30分より
会場:道の駅「和」 道路情報センター内伝統芸能常設館
入場料(協力金):大人300円、小中学生100円
問い合わせ先:道の駅「和」道路情報センター
電話:0771-84-1522
※都合により、休演、日程変更、公演発表内容が変更となる場合もございます。
お問い合わせ
南丹広域振興局地域連携・振興部 企画・連携推進課
亀岡市荒塚町1-4-1
電話番号:0771-24-8430
ファックス:0771-24-4683