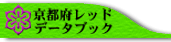| 選定理由 |
今のところ、日本では京都府に数株が知られるのみである。 |
| 分布 |
本州(京都府)、中国大陸。
◎府内の分布区域
南部地域(京都市)。 |
| 生存に対する脅威 |
森林遷移。 |
| 必要な保全対策 |
唯一の産地は杉林のため暗くなり、衰えてゆく傾向にある。胞子からの人工繁殖・維持が望ましい。 |
| 特記事項 |
日本では最近認識されたため、他のレッドデータブックには記載がない。 |
| 形態 |
夏緑性の多年草。根茎は短く這い、葉を接近して出す。葉は長さ60〜80cm、幅20〜30cm、2回羽状深裂、最下の羽片はやや短縮する。羽片の裂片は接近してつき、深い鈍鋸歯がある。側脈は2〜3岐する。ソ−ラスはやや中肋寄りにつき、包膜は楕円形からJ型、稀にU型、全縁。
◎近似種との区別
オオメシダは葉がはるかに大型で、包膜の縁は細裂する。コウライイヌワラビは羽片の裂片が細く、やや間隔をおいて並ぶので、羽軸にそって狭い翼ができる。また側脈は単条から2岐まで。
◎参照 新日本植物誌 シダ;pl.481a(1992)(ただし481頁の文章はコウライイヌワラビの記述であるから除く) |