ここから本文です。
京都府立植物園 見ごろの植物情報 平成24年8月17日
こちらでは現在見頃の植物を紹介しています。
科名等の変更について(おしらせ)
植物の分類については、分子生物学の発展によって個々の植物のDNA解析が行われるようになりました。その解析結果や、近年の研究に基づく分類体系が世界的に採用されるようになり、当園ホームページ「見ごろの植物情報」の表記につきましても、2011年4月以降は新しい分類体系で表示しています。科名は新科名のみの表示とします。
平成24年8月17日(金曜)現在
観覧温室では

サガリバナ
Barringtonia racemosa
サガリバナ科(ジャングルゾーン)
東南アジアから太平洋諸島の湿地に分布します。薄いピンク色で糸状に広がっている部分は雄しべです。その下に短い花弁がつきます。花序は長さ50センチ以上になり、15から20花をつけます。夜に開花し、朝には落ちているので開花した状態は観察できませんが、落ちた花を水鉢に浮かべていますので、きれいな状態で観察できます。芳香があります。見頃は9月上旬まで。

ツンベルギア バッティスコムベイ
Thunbergia battiscombei
キツネノマゴ科(ジャングルゾーン)
熱帯アフリカ原産。花は濃青色で、中心が黄色となります。見頃は8月下旬まで。

キバナキョウチクトウ
Thevetia peruviana
キョウチクトウ科 (ジャングルゾーン)
熱帯アメリカ原産。高さ5メートルになる低木で、葉は細く長さ約15センチになります。花は黄色でややねじれた鐘状になります。見頃は8月下旬まで。

コプシア フルティコサ
Kopsia fruticosa
キョウチクトウ科 (ジャングルゾーン)
インド、ミャンマー、マレー半島原産。高さ6メートルほどになる常緑低木です。花は淡紅色で口部はさらに濃い色となり、ニチニチソウを思わせます。見頃は9月上旬まで。

カカオ
Theobroma cacao
アオイ科(熱帯有用作物室)
当園の管理条件下では結実しないため、人工交配をしています。種子を炒って粉末にして砂糖、香料等を混ぜ、圧して固めたものがチョコレートで、粉末を圧搾して脂分を除いたものがココアです。見頃は8月下旬まで。

ヘリコニア ロストラタ
Heliconia rostrata
オウムバナ科 (ジャングルゾ-ン)
アルゼンチン、ペルー原産。高さ1から6メートルになり、赤と黄色の花序を垂れ下げます。見頃は8月下旬まで。

グラマトフィルム スペキオスム
Grammatophyllum speciosum
ラン科(ラン室)
ミャンマー、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ニューギニア原産。ラン科最大の種類で、タイガーオーキッ ドとも呼ばれています。本個体は白色地の花弁に赤褐色の斑点が多く入るタイプ(wallisii form)で、フィリピンから導入されたものです。見頃は8月下旬まで。

ペリステリア エラタ
Peristeria elata
ラン科(ラン室)
コスタリカ、パナマ、コロンビア原産。パナマの国花で、花の中にハトがいるように見えるため、「鳩蘭」の名前でも呼ばれています。見頃は8月下旬まで。

ホウガンノキ(果実)
Couroupita guianensis
サガリバナ科(アナナス室)
南アメリカ原産の高木で、花序は長さ60から90センチの総状花序で下垂し、幹あるいは太い枝に直接生じます。花は直径約10センチで、内側は紫色を帯びた紅色、外側は黄色でやや赤色を帯びます。果実は球形で直径約15から20センチになります。見頃は9月下旬まで。

ペトレオウィテクス ヴォルフェイ
Petraeovitex wolfei
シソ科(中庭)
マレー半島原産のつる性植物。茎の先端や先端付近の葉腋から黄色に色付いた花序を垂れ下げます。花のように見えるのは苞で、その中から直径約1センチの淡黄白色花が咲きます。見頃は9月上旬まで。

マツカサジンジャー
Tapeinochilos ananassae
オオホザキアヤメ科(ジャングルゾーン)
インドネシアからオーストラリアのクィーンズランド州原産。高さ約2メートルになる多年草で、コスツス属のように葉がらせん状につきます。松かさ状の苞は赤色で、その間から黄色の花がつきます。見頃は8月下旬まで。

バナナ (果実)
Musa acuminata cvs.
バショウ科(熱帯有用作物室)
葉が40枚前後出た後に赤紫色の花房を形成します。花房は下垂して伸び、最初の10段程は子房が発達する雌花群で、その後は中性花または雄性花で子房は発達しません。見頃は8月下旬まで。

ディモルフォルキス ロウイ
Dimorphorchis lowii
ラン科(冷房室)
ボルネオ原産の大型の着生ランで、花茎は長く下垂します。花茎の基部につく2から3花は黄色地に赤褐色の斑点が入り、他の花は白色地に赤褐色斑となります。1つの花茎に2つの異なる形態の花を咲かせるランは、ディモルフォルキス属の2種だけで、その理由は解明されていません。見頃は8月下旬まで。

ソーセージノキ(果実)
Kigelia pinnata
ノウゼンカズラ科(ラン室)
アフリカ原産です。長さ30から50センチ、直径10センチ程度のソーセージにそっくりの果実を垂らすことからソーセージノキと名付けられています。果肉は硬く繊維質で食用にはなりませんが、種子は食用にされることもあります。ゾウ、サイなど大型の哺乳動物が果実を食べて種子を散布します。見頃は8月下旬まで。

バオバブ
Adansonia digitata
アオイ科(砂漠サバンナ室)
アフリカのサバンナ地域に広く分布。花は白色で夜に開花し、翌日の午前中でしおれてしまいます。
園内樹木ほかでは

キョウチクトウ
Nerium oleander
キョウチクトウ科(桜林西ほか)
インド原産で中国には明の時代、日本には江戸時代中期に渡来したと伝わる常緑の小高木です。和名は夾竹桃と表し、葉が竹に似て花は桃に似ているという形質の特徴から付いたものとされます。花の少なくなる夏季に長く咲くことから修景木として公園や庭園、緑地などによく植栽されますが有毒植物でもあります。

エゾミソハギ
Lythrum salicaria
ミソハギ科(植物生態園)
北海道から九州までの各地、ユーラシア大陸や北アフリカにも広く分布する多年草。北海道に多いことからこの和名がつきますが九州以北の中栄養の湿地で普通に見られます。属名はギリシャ語の「血」に由来し、赤い花色から命名されました。

キキョウ
Platycodon grandiflorus
キキョウ科(植物生態園)
日本全土、朝鮮半島、中国、東シベリアに分布する多年草。根にはサポニンという成分を含み生薬として去痰、鎮咳、鎮痛、鎮静、解熱などに利用されます。自生株は減少傾向にあり絶滅が危惧されています。

カワラナデシコ
Dianthus superbus var. longicalycinus
ナデシコ科(植物生態園)
秋の七草のひとつ、撫子と呼ばれる多年草。日当たりのよい草原や河原に自生し、以前は手入れが継続されてきた里山的環境で多く見られましたが、管理された里山の減少により、自生地や個体数は減少傾向にあります。ロンドンオリンピックで銀メダルを獲得した女子サッカー日本代表チームの愛称でもよく知られます。

フシグロセンノウ
Silene miqueliana
ナデシコ科(植物生態園)
日本の固有種で、山地の林下などに生える多年草。節が太く黒紫色を帯びることが和名の由来です。日本の野草では珍しい色の朱赤色の花を付けることが大きな特徴です。

ヒオウギ
Iris domestica
アヤメ科(植物生態園)
茎は高さ50から120cmになり、その下方に長さが30から50cmほどの広剣状の扁平な葉を扇形に付けることからこの和名で呼ばれます。種子は光沢のある球状になり「うば玉」や「ぬば玉」と呼ばれます。

カリガネソウ
Caryopteris divaricata
シソ科(植物生態園)
東アジアに分布し、日本では山地の日当たりのよい場所に自生します。花弁は5枚で縁がひだ状になり、上に 2枚、下左右へは各 1枚ずつ大きく広がり、下側の花弁が舌状になり紋様が入っています。別名ではホカケソウ(帆掛草)とも呼ばれます。

レンゲショウマ
Anemonopsis macrophylla
キンポウゲ科(植物生態園)
日本特産で1属1種の多年草。萼も花弁も共に花弁状に見えるが、萼は平らに開き、花弁は抱えるように咲くため、一見では二段構えに花弁が並んでいるようにも見えます。複数の都道府県で絶滅危惧種に指定されています。漢字では「蓮華升麻」と表記。

ゼンテイカ
Hemerocallis dumortieri var. esculenta
キスゲ科(植物生態園)
本州中部以北、北海道、南千島、樺太に分布する多年草。和名は漢字で“禅庭花”と表記しますが「ニッコウキスゲ」の別名でもしばしば呼ばれます。朝方に開花すると夕方にはしぼんでしまう一日花。

トウテイラン
Veronica ornata
ゴマノハグサ科(植物生態園)
近畿から山陰地方の限られた海岸沿いに自生する日本固有の多年草。和名の意味は花の色が中国の洞庭湖の水のような色で美しいところからと言われます。

カノコユリ
Lilium speciosum
ユリ科(植物生態園)
花被片上の紅色斑点が鹿の子絞り模様に似ることからこの和名で呼ばれます。九州、四国のほか台湾、中国にも分布します。かつて欧米に紹介されて以来、海外でも非常に人気があり輸出もされています。庭植えのほか切り花やコサージュなどにも用いられます。

サルスベリ
Lagerstroemia indica
ミソハギ科(桜林西ほか)
花木の少ない夏を代表する中国南部原産の落葉高木。古い樹皮のコルク層が剥がれ落ちすべすべした触感の幹肌が特徴で、このことから木登りの得意な猿でも滑り落ちそうだというのが和名の由来です。円錐花序に咲く花の形も特徴的で近寄って観察すると複雑な形がよくわかります。
 ‘白祇園守’
‘白祇園守’
 ‘日の丸’
‘日の丸’
 ‘宋旦’
‘宋旦’
 ‘紫玉’
‘紫玉’
 ‘紅孔雀’
‘紅孔雀’
 ‘角倉花笠’
‘角倉花笠’
 ‘コエレスティス’
‘コエレスティス’
 ‘ピンクデライト’
‘ピンクデライト’
 ‘ザバナー’
‘ザバナー’
 ‘白乱’
‘白乱’
 ‘ラージホワイト’
‘ラージホワイト’
 ‘ルーシー’
‘ルーシー’
ムクゲ
Hibiscus syriacus
アオイ科(桜品種見本園前)
ムクゲは中国原産とされ、日本にも野生しますが真の自生か帰化したものか明らかでないとされます。江戸時代から園芸品種が育成され『木草図譜』(1828)にも多数の花が掲載されているほか欧米でも多くの園芸品種が作出されました。一日花ですが次々に花をつけていき長く鑑賞できます。
四季 彩の丘では
ハス
Nelumbo
ハス科
ハスは花を観賞用、根を食用にと、古くから日本人の生活に根付いてきた植物です。とくに観賞用に品種改良が行われてきた園芸品種は、「花ハス」と呼ばれます。
ハス(ネルンボ)属は2種の原種を含んでおり、熱帯、温帯アジアからオーストラリアにかけて分布するハス Nelumbo nucifera と、北アメリカ南部から中央アメリカ北部にかけて分布するキバナハス Nelumbo lutea が存在します。
また園内では、巨椋池(おぐらいけ)由来の品種の展示も行っています。巨椋池は、かつて伏見区、宇治市、久御山町が接している場所に存在した湖です。
干拓事業によって今は農地になっていますが、かつては花ハスの生産、観光で有名でした。そのため今でも跡地からハスが芽生えることがあり、それらは巨椋池の花ハスの名残りとして認知されています。

`嘉祥蓮’ Kasyo-ren

`精華’ Seika
温帯スイレン
Nymphaea cvs.
スイレン科
四季 彩の丘の池で育てている主なスイレンは、温帯スイレンと呼ばれる寒さに強い園芸品種のグループです。
スイレンには昼間に開花し、屋外で越冬できる温帯スイレンと、夜間もしくは昼間に開花し、加温設備がないと越冬できない熱帯スイレンの2種類があります。温帯スイレンは根茎を伸ばして生育しますが、熱帯スイレンは球根を作ります。
温帯スイレンはフランスを中心に品種改良が行われたものが多くあります。昼過ぎには花が閉じてしまうため、午前中の観察がおすすめです。
また、スイレンとハスの違いについて質問をいただくことがよくありますが、スイレンの葉には切れ込みが入ること、ハスのように葉が水をはじかないことで見分けられます。

`ファビオラ’ `Fabiola’

`ゴンネール’ `Gonnere’
ヒョウタン
Lagenaria siceraria ssp. siceraria
ウリ科
ヒョウタンは北アフリカ原産の作物であると考えられています。日本には紀元前の古い時代にもたらされ、飲料を保存するための容器になる作物として重要な存在でした。
日本のみならず世界中にヒョウタンの文化があり、楽器として利用している国も多いです。分類上では、カンピョウの原料になるユウガオ Lagenaria siceraria ssp. hispida と同種であるとされています。

`大瓢タワー’ `Ohyo-tower’

`梵鐘’ `Bonsho’

`縮緬いぼ’ `Chirimen-ibo’

`マランカ’ `Maranka’
園内花壇では
沈床花壇では、約20品種150株のヒマワリが見頃をむかえています。
ヒマワリ
Helianthus annuus cv.
キク科(沈床花壇)
北アメリカ原産。草丈は90から200センチになり、株全体に短くてかたい毛があります。葉は互生し、大きな長楕円形で、先端がとがり、長い葉柄があります。頭花は頂生し、ふつうは舌状花と筒状花からなりますが、園芸品種によっては筒状花のみからなるものもあります。花色は黄色または淡橙黄色で、赤褐色のものもあります。花径は7から30センチで、園芸品種によっては40センチを超えるものもあります。花壇や切り花に利用するほかに、種子からひまわり油をつくり、食用や製菓用にします。見頃は9月中旬まで。

‘サンリッチオレンジ’‘Sunrich Orange’
花弁の重ねが多く、並びの整った花形です。花弁は濃いめのオレンジ色。芯は黒褐色です。 世界で一番切り花にされている品種

‘クラレット’‘Claret’
花色が濃いワインレッドで分枝性の品種です。

‘ダブルシャイン’‘Double Shine’
八重咲き分枝系の品種です。花色は鮮やかな橙色。花色・花姿・草丈などに多少個体差があります。

‘バレンタイン’‘Valentine’
鮮明なクリームイエローで、花弁が多く、中心部は黒色です。茎の上部でよく枝分かれします。

‘プラドレッド’‘Prado Red’
草丈120から140センチの中高性種のヒマワリです。分枝性に優れ、若干色幅が出ますが濃赤色の豪華な花が咲きます。

‘モネのひまわり’‘Monet no Himawari’
画家シリーズのひとつです。花色は鮮やかなレモンイエロー。八重咲き品種です。

‘リングオブファイヤー’‘Ring of Fire’
花弁は芯に近いほど赤く外側が濃いオレンジのツートンカラーです。茎の上部でよく枝分かれします。海外で育成された品種で、花色・花姿・草丈などに多少個体差があります。 オールアメリカセレクションズ(All America Selections:全米審査会)2001年の金賞受賞品種です。

‘レモンエクエア’‘Lemon Eclair’
珍しいセミダブル咲きの品種です。花色はレモンイエローで、中心部は褐色を帯びます。

‘ココア’‘Cocoa’
濃い褐色の花色が特徴です。茎の上部で5から8本の枝がスプレー状に分枝し、その先に花が咲くため観賞期間の長い品種です。

‘ロシア’‘Rossian’
草丈は2から3メートルに達します。先端が明るい黄色をした花径約30センチの巨大な花を一輪咲かせます。ロシアでは一般的で多く栽培されているのでこの名前がつきました。

ハゲイトウ
Amaranthus tricolor cv.
ヒユ科(北山ワイルドガーデン、洋風庭園東)
熱帯アジア原産し、耐寒性はないです。草丈80から150センチ。茎は無毛で肥厚します。葉の形は被針形、線形、長楕円形と様々あります。花は球形で葉腋に群生します。本種の葉は、初めは緑色で8月ごろから頂葉が黄色、淡紅色から紅色、緑色の3色になったり、黄色、紅色、紫紅色、緑色の4色となり、秋にもっとも美しくなります。見頃は9月上旬まで。

ソライロアサガオ‘ヘブンリーブルー’
Ipomoea tricolor ‘Heavenly Blue’
ヒルガオ科(会館前)
メキシコ、中央アメリカ、西インド諸島、熱帯南アメリカに分布。植物体全体に毛のないつる性多年草。葉は卵形、花柄は葉柄より長いので花が目立ち、また1花序当たりの花数も多く順次開花します。花は漏斗形で、花冠は紫色または青色、花筒上部は白、下部は黄色です。土壌伝染性のバクテリアにより立ち枯れ症状をおこすことがあります。見頃は10月下旬まで。

ショクヨウホオズキ
Physalis pruinosa cv.
ナス科(北山門前)
北アメリカから熱帯アメリカにかけて原産します。茎は下位節までよく分枝し、地上近くを這い、ときに30センチほどの高さに立ち上がります。花喉部には5つ褐色の斑点があります。果実を包む宿存萼は完熟すると淡褐色となり、提灯のように見えます。果実は熟すると黄色となり、径1.5から2センチ。味は甘酸っぱいが、やや苦みのあるものもあります。

ペンタス
Pentas lanceolata cv.
アカネ科(洋風庭園東)
東熱帯アフリカからアラビア半島南部の原産です。常緑の多年草で、草丈30から130センチ、基部は木質化します。全体に柔毛を密布します。花は茎頂に頭状につき、花筒は長さ1.5から2センチです。見頃は9月上旬まで。

ベゴニア‘ドラゴンウィング’
Begonia semperflorens ‘Dragon Wing’
シュウカイドウ科(北山門前)
南米原産。最初アメリカで改良されたものがドイツでさらに改良された品種です。草丈は15から40センチ。独特の羽のように広がる草姿で、株張りは30から40センチ。花も大きく、色は赤、桃色の2色で、濃い特徴的な緑葉とのコントラストが美しいです。性質は強健です。見頃は10月上旬まで。

ネコノヒゲ‘チャイナブルー’
Orthosiphon aristatus ‘China Blue’
シソ科(北山ワイルドガーデン)
インド、マレーシア原産の多年草です。草丈40から60センチです。茎には稜があり四角形。葉は対生または輪生し、卵形または三角形で鋭尖頭です。花序は頂生し、花は2から6個、輪生して下部から開花します。また利尿剤、血圧降下剤として知られる薬用植物でもあります。見頃は9月上旬まで。

ニコチアナ グランディフロラ
Nicotiana grandiflora
ナス科(沈床花壇)
ブラジル南部原産。草丈1から1.5メートルになります。葉は卵状楕円形で長さは約30センチ。花序は短い総状で数花がつき、花冠は白色で外側は緑色を帯び、筒部は長さ6から12センチになり、先は広く広がるので、喉部では径1センチくらいです。見頃は9月上旬まで。

クレオメ
Cleome hassleriana cv.
フウチョウソウ科(観覧温室前、北山ワイルドガーデン)
熱帯アメリカ原産。茎は高さ80から100センチで直立します。茎の上方に総状花序をつけ、長い柄のある4弁花を下から順に咲かせます。4個の雄しべが長く突出し、チョウが舞う姿を連想させます。見頃は9月上旬まで。

カンナ‘アメリカンレッドクロス’
Canna ‘American Red Cross’
カンナ科(正門前花壇、沈床花壇)
熱帯アメリカ原産。草丈は50から200センチです。花は鮮やかな緋紅色で大輪咲き。性質は大変強く、耐暑性・耐寒性が共に優れ、乾燥や病害虫にも強いです。見頃は9月下旬まで。
ガイラルディア アリスタタ
Gaillardia aristata cvs.
キク科
北アメリカ中南部からニューメキシコ原産。草丈60から90センチくらいで、よく分枝します。葉は互生し、上方の葉は被針形ないし長楕円形、下方の葉は根出し、へら形で、全縁または粗い波状鋸歯縁となります。茎葉全体に多くの粗い毛があります。頭花は径6から10センチくらい。舌状花の先端部は黄色で、基部は紫紅色です。

ガイラルディア‘アリゾナサン’
Gaillardia aristata ‘Arizona Sun’
キク科(北山ワイルドガーデン)
オールアメリカセレクションズ(All America Selections:全米審査会)、フロロセレクト(Fleuroselect:欧州花き種苗審査会)の金賞受賞品種です。見頃は9月上旬まで。
ガイラルディア プルケラ
Gaillardia pulchella cvs.
キク科
北アメリカ東南部からメキシコ北部、さらにニュー・メキシコからモンタナにかけて原産します。草丈30から50センチくらいで直立し、よく分枝します。葉は広被針形ないし長楕円形で無柄、上方の葉は全縁で鈍頭、下方の葉は歯状となるか羽状に裂けます。茎葉全体が軟毛におおわれています。頭花は径5センチくらい。舌状花の先端部は黄色、基部は紫紅色です。

ガイラルディア‘レッドプルーム’
Gaillardia pulchella ‘Red Plume’
キク科(北山ワイルドガーデン)
見頃は9月上旬まで。

ガイラルディア‘ダズラーミックス’
Gaillardia pulchella ‘Dazzler Mix’
キク科(北山ワイルドガーデン)
見頃は9月上旬まで。

エキナケア‘パウワウワイルドベリー’
Echinacea prupurea ‘Pow Wow Wild Berry’
キク科(北山ワイルドガーデン)
アメリカのオハイオ州からジョージア州にかけて自生しています。茎は無毛で、草丈60から100センチになります。茎葉は被針形、葉縁に鋸歯がつき、無柄。頭花は茎頂に1個つき、径約10センチ。舌状花の色は紫紅です。花の形がまといの馬簾に似ているところから、ムラサキバレンギクという和名があります。オールアメリカセレクションズ(All America Selections:全米審査会)2007年の金賞受賞品種です。見頃は10月中旬まで。

ナス‘甲子園’
Solanum melongena ‘Koshien’
ナス科(北山ワイルドガーデン)
ナスは熱帯では多年草であるが、日本などの温帯では一年生作物としてよく栽培されています。茎はよく分枝して、小低木状となります。果色は黒紫色、鮮紫色、緑色があります。本種は白色で熟果は黄色となります。見頃は10月上旬まで。

トウガラシ‘ブラックパール’
Capsicum annuum ‘Black Pearl’
ナス科(北山ワイルドガーデン)
中央・南アメリカに分布。草丈70から80センチになります。生育初期の葉色は緑ですが、高温と高日照により黒く変化します。果実の色は、真珠のような光沢をだす黒色から、熟すと赤色になります。耐暑性、耐乾性にとても優れ、生育旺盛です。オールアメリカセレクションズ(All America Selections:全米審査会)2006年の金賞受賞品種です。見頃は10月上旬まで。

アメリカフヨウ‘サウザンベル’
Hibiscus moscheutos ‘Thousan Bell’
アオイ科(北山ワイルドガーデン)
北アメリカ原産の大型多年草。草丈1から1.8メートルになります。葉は卵形。花は上部の葉腋に単生しますが、散房花序の状態になることがあります。‘サウザンベル’は日本で改良された品種で花茎30センチに達する巨大輪を咲かせます。

モモイロキダチチョウセンアサガオ
Brugmansia hyb.
ナス科(会館前)
ペルーのアンデス山脈の低斜面に分布し、エクアドルその他で栽培されています。ブラジル中部原産で、花が淡黄色から開くと白色になる B. suaveolens とエクアドル産の橙赤色の花をつける B. versicolor との交雑種であるとされています。葉は長楕円形、葉柄をもち垂れます。花冠はラッパ状、花色は淡黄色から淡紅色、赤桃色にかわります。見頃は9月下旬まで。
植物園スタンプラリー
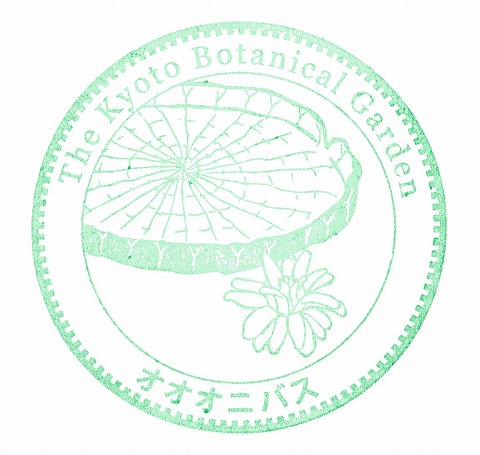
8月はオオオニバスです。
7月の答えは「ブーゲンビレア」です。
z
お問い合わせ
文化生活部文化生活総務課 植物園
京都市左京区下鴨半木町
電話番号:075-701-0141
ファックス:075-701-0142