ここから本文です。
文化・教育常任委員会管外調査(平成28年1月19日~1月21日)
川崎市立はるひ野小中学校(神奈川県川崎市)
小中一貫教育に適した学校施設について
川崎市立はるひ野小学校・同はるひ野中学校は、平成20年4月、施設一体型の小中連携校として開校しました。背景としては、平成2年から土地区画整理事業が進められた川崎市麻生区黒川・はるひ野地区に、まちづくりの核となるべき公共施設として、小学校の建設が予定されていましたが、地域の要望により中学校も同時に建設することとなり、その後、学校建築の有識者も加わる基本計画検討委員会での議論を経て、同19年1月にPFI事業として学校建設に着手されたものです。
同校は、開校当時、児童生徒合わせて600名でありましたが、開校8年目を迎え、小学部児童1,072名、中学部生徒369名の合計1,400名となっています。
基本理念は、1.小中学校9年間を通じて人間形成を実現する、2.今日的な教育課題に対して小中学校9年間を通じて対応する、3.小中学校の教育の融合を図り、新たな学校文化の創出を図る、ことです。
同校の教育課程の特徴は、校舎合築を生かし、児童生徒の成長過程を見直した教育として、小中学校のより確かな連携を目指し、9年間を4-3-2の3ブロックに分けた教育課程編成が行われています。また、ハートフルはるひ野プランを核に心豊かな児童生徒の育成に取り組んでいます。ハートフルはるひ野プランは、豊かに生きる(自分づくり)、健やかに生きるという在り方生き方教育であり、3つの合言葉、1.あいさつは心の窓、2.ありがとうは魔法の言葉、3.そうじは心を磨く、に集約されています。
学校運営においては、学校ごとに校長が配置され、適宜連携が図られています。管理職を除く全教職員に対して兼務発令がされており、9年間を通して児童生徒の成長を見守っています。
特色ある教育活動では、小中連携の取組として、全校で取り組むスポーツフェスティバルやアートフェスティバルの開催、小中合同朝会やブロック集会の実施、中学生が小学校の学習をサポートする授業や活動の実施、また、教職員の授業力向上のための小中合同研修や校内授業研究の実施などが実践されているとのことです。
施設を有効に活用した教育活動も行われています。校舎内には、大小様々な特別教室が設置され、多様な活動が展開されています。中学部では全教科に教科教室があり、毎時間生徒が教室を移動し各教室で各教科の独自性を生かした授業が行われています。教室前のオープンスペースは、交流学習や展示、学年集会に使用したり、小学部1、2年生の教室にあるパオと呼ばれる小部屋をはじめ、各学年の小部屋は、落ち着いた話し合いの場や、少人数での学習の場として使用されています。
また、小中の職員室(校務センター)を一体化し、校門、中庭、校庭が見渡せるように配置し、校内に地域交流センター、わくわくプラザ等を設け、学校が地域コミュニケーションの核として機能できる整備も行われています。
はるひ野小中学校としては、今後、小中9年間のつながりを検証するとともに、ハートフルはるひ野プランに重点を置き、地域への恩返しをしながら、小中学校の連携教育に一層取り組んでいきたいとのことでした。
主な質疑
- 学年区分4-3-2制における小学校5、6年生のリーダー性について
- 小中連携校における教員の負担について
- 4-3-2制による成果について
- 教員の異動状況について
- 川崎市における学級編成基準について など


概要説明を聴取した後、学校の主な施設を視察
東京都立小石川中等教育学校(東京都文京区)
同校の概要について
東京都立小石川中等教育学校は、大正7年、前身となる東京府立第五中学校が小石川区駕籠町に創立されました。東京都制施行と学制変更を経て、昭和25年、都立小石川高等学校と校名が改称され、平成18年に同校を母体として都立小石川中等教育学校が開校、同23年、小石川高校が閉校して都立初の中等教育学校に完全移行しました。学年は1~6年までで、1~3年生が前期課程、4~6年生が後期課程となり、後期課程からの入学はありません。
同校は、創立以来、90年以上にわたって受け継がれてきた「立志」「開拓」「創作」の精神を教育理念の中核に据え、「自ら志を立て(立志)、自分が進む道を自ら切り拓き(開拓)、新しい文化を創り出す(創作)」ことのできる人材の育成に努めています。そして、その教育理念を実現するための方策として、「小石川教養主義」「理数教育」「国際理解教育」を推進しています。
小石川教養主義とは、全ての教科・科目を学ぶことによって、単に受験のためではない教養を生徒に身に付けさせるもので、同校の伝統を引き継いでいます。小石川教養主義の象徴とも言える学校設定科目「小石川フィロソフィー」など、特色ある授業が進められています。
理数教育については、文部科学省よりSSH(スーパーサイエンスハイスクール)の指定を受け、全生徒を対象にSSH事業が展開されています。都立小石川高校での指定と通算して10年間の指定となり、さらにコアSSHの指定も受け、日本学術会議、大学や海外の理数系教育重点校などと連携し、サイエンスカフェ、オープンラボや小石川セミナーなど、さまざまな活動を行っています。
国際理解教育としては、充実した英語教育により、生徒は高い総合的な英語能力を身に付けられるようになっています。全員が参加する国内語学研修、海外語学研修、海外修学旅行では、身に付けた英語を用いて、異文化理解、学校交流や意見発表等に取り組んでいます。また、同校は、東京都教育委員会から、次代を担うグローバル人材育成に向けた学校の取組を支援するために、都立高校及び都立中等教育学校の中から10校を選定する東京グローバル10に指定されています。
その他、大学や研究機関との連携も図られており、1年から5年まで、教科の学習との連携を図り、大学や研究所とも連携しながら、知を深めるための総合学習を行い、生徒の知的好奇心を育てています。
小石川中等教育学校としては、今後も、「立志」「開拓」「創作」の精神のもと、国際社会で活躍できる人材の育成に一層努めていきたいとのことでした。
主な質疑
- 教員の英語力について
- 前期課程(義務教育)の教育内容について
- 生徒の将来の夢について など
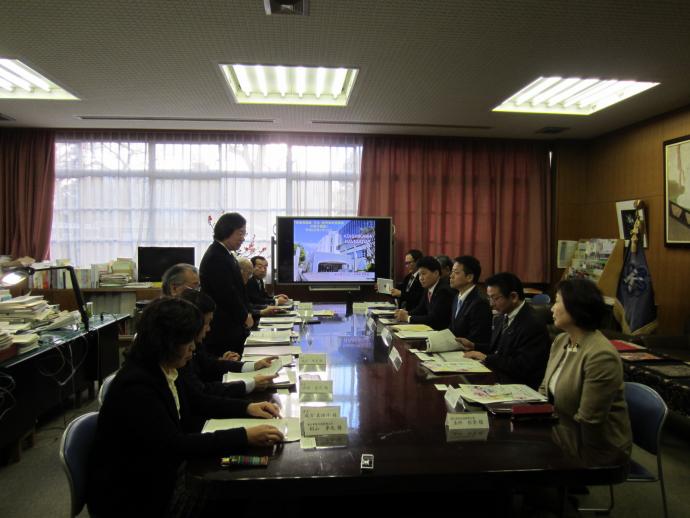

概要説明を聴取した後、学校の主な施設を視察
三鷹市星と森と絵本の家(東京都三鷹市)
子どもたちが豊かに成長する地域文化創造のための取組について
三鷹市は、武蔵野の面影を残したまちとして、多くの作家や芸術家から愛されてきており、このような風土や環境を背景に、従来から市民の文化活動も活発に行われています。そのような中、同市では、平成18年度から「みたか・子どもと絵本プロジェクト」に取り組んでいます。同プロジェクトは、絵本を通じて、子どもたちがふれあいの中で生き生きと豊かに成長することができる地域文化の創造を願う取組で、子どもと絵本に関わる担い手の養成や絵本を仲立ちとして地域のさまざまな活動や資源をつなぎ、市民との協働により人々の交流と創造の場をつくり出す活動が、三鷹市全域で展開されています。
「三鷹市星と森と絵本の家」は、平成21年7月7日、「みたか・子どもと絵本プロジェクト」の理念のもとに、その特色ある拠点として国立天文台三鷹キャンパス内に整備されました。「星と森と絵本の家」は、三鷹市が国立天文台の協力のもとに運営する個性豊かな施設です。その特徴としては、「星」は国立天文台の知的資源の活用や天文学者等の協力、「森」は天文台の森の豊かな自然の中にあるという環境、「絵本」は子どもと絵本の活動に集う多彩な人々との協働、「家」は大正時代の官舎を保存活用した建物の魅力、になっています。施設は、国立天文台内にあった旧1号官舎(大正4年に高等官官舎として建設)を保存活用しており、平成21年5月に三鷹市登録有形文化財第1号に指定されています。
絵本の家は小さな施設ですが、3つのテーマ展示が行われています。旧玄関の建築展示室は、家の構造や設計図面等の常設展示、絵本展示室は、絵本を通じて星や自然に関心が高まるよう年間テーマを決める企画展で体験型展示が行われ、回廊ギャラリーでは、絵本の家で公募した星や宇宙に関する絵本の原画が展示されています。また、読書室には、約2,500冊もの絵本を所蔵し、本棚は「星-地球」「森-植物」「ひと・くらし・ことば」の分類を軸に、物語や科学絵本が分かりやすく配列されています。本の貸し出しは行われていませんが、家の中であれば、どこでも自由に読むことができます。
豊かな自然を残す天文台の森に囲まれた家の中庭では、週末などにボランティアによるクラフト体験ができ、天文台の中に生えていた草花を集めた草壇があり、雑草として抜かれてしまう植物も大切に育てているとのことです。
このような取組をする中、絵本の家は、平成27年7月7日に20万人目の来場者を迎えました。
星と森と絵本の家としては、今後も、多様な人々による創造的な活動と交流を通して、子どもたちが豊かに成長する地域文化の形成に寄与していきたいとのことでした。
主な質疑
- 来館者数の集計方法について
- 学校との連携について
- 国立施設内における運営の課題等について
- 国立天文台とのセキュリティ上の調整について
- 特別展の予定について など


概要説明を聴取した後、施設を視察
東京国立博物館(東京都台東区)
同博物館の概要について
東京国立博物館は、明治5年に創立された日本で最も長い歴史を持つ博物館です。日本の総合的な博物館として、数多くの国宝、重要文化財をはじめ、11万6千件にのぼる収蔵品を所蔵し、日本を中心に広く東洋諸地域の美術品や考古資料などの文化財を守り伝える中心的な役割を担い、有形文化財の収集、保管、修復、展示、調査研究、教育普及などの事業を行っています。
平成13年4月、東京、京都そして奈良の3つの国立博物館を運営する独立行政法人国立博物館が発足し、さらに同19年4月には独立行政法人文化財研究所と統合され、独立行政法人国立文化財機構となり、現在は、同機構が4つの国立博物館を運営しています。
東京国立博物館の運営経費は、約22億円で、うち約4分の3は国からの交付金により支えられており、国の財政状況が厳しい中、入館料を抑えながら展示活動以外にも多くの活動を実施し、経費節減と自己収入の拡大に努めているとのことです。
同博物館は、独立行政法人化後、民間の手法を学び取り入れることでサービス面の向上を目指し、来館者が何を求めているかを考え、さまざまな取組を進めています。最近では、託児サービスも実施し、子育て中のお客様にも展示を楽しんでいただけるよう、専用託児室で美術館や博物館での託児経験豊富なスタッフが責任を持って対応しているとのことです。また年間約200万人の来館者のうち4割は外国人の方のため、館内を案内する表記は8箇国語の表記にするなど、利用しやすい博物館となるよう取り組まれています。
同博物館は6つの展示館を有しており、魅力ある総合文化展を目指し様々な企画が実施されています。総合文化展は、収蔵品、寄託品を展示するもので展示事業の中核をなしており、年間300回程度の展示替を定期的に実施し、平成27年度は約7,200件の文化財を展示・公開する予定とのことでした。重要文化財の本館は、2階は縄文時代から江戸時代までの日本美術の流れをたどる時代別展示、1階は彫刻や陶磁などの分野別展示やテーマ別展示で構成されています。東洋館では、日本以外の東洋の美術、工芸、考古遺物などが展示されています。平成館は、1階に考古展示室、企画展示室やラウンジ、約400席の大講堂があり、2階には約3,000平方メートルに及ぶ特別展専用の展示室があります。考古展示室では、土偶や銅鐸、埴輪など発掘された文化財から日本の歴史をたどるようになっています。調査訪問時には、特別展「始皇帝と大兵馬俑」が開催中で、国内外から多くの人が来館されていました。法隆寺宝物館は、奈良の法隆寺から皇室に献納された宝物300件余りを収蔵・展示し、表慶館は、近年は特別展の展示会場として活用され、黒田記念館は、日本近代画家・黒田清輝の作品が展示・公開されています。
東京国立博物館としては、訪れた人が多くの感動を体験し、博物館という空間を心から楽しみ、また、日本の一大文化発信拠点となるように、国民が世界に誇れる博物館を目指して、一層努力していきたいとのことでした。

横浜市立東山田中学校(神奈川県横浜市)
学校と地域をむすぶ取組について
横浜市立東山田中学校は、横浜市の北部、都筑区の港北ニュータウンにあります。同区は人口約21 万人で、横浜の副都心として開発された新興住宅地域です。
東山田中学校は、平成17年4月に開校し、横浜市教育委員会により、開かれた学校づくりを推進するモデル校として、横浜市そして神奈川県初のコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)として指定されました。学校運営協議会は、町内会代表や小中学校PTA会長といった地域や保護者代表、大学教授などの学識経験者などが委員となって構成され、毎月1回開催され、教職員全員と懇談したり、学校運営や教育活動の審議、他の地域との情報交換や学校支援地域本部との連携など、学校運営に地域住民の声を反映させるための協議の場となっています。
同校の最大の特徴は、中学校内にあるコミュニティハウスです。東山田中学校コミュニティハウスは、設計段階から学校と地域の連携施設として考慮され、中学校の中庭に面し、解放された廊下で中学校とつながっており、身近な生涯学習活動の場、地域活動の場、そして、大人も子どもも共に学び交流する施設として幅広く利用されています。また、地域と学校を結ぶ場として、東山田中学校区学校支援地域本部(やまたろう本部)が設置され、学校の教育活動を支援するため、地域住民の学校支援活動への参加をコーディネートする、地域につくられた学校の応援団となっています。同校は、コミュニティ・スクールと学校支援地域本部の2つの機能を有することにより、地域の中核としての学校を目指しています。
同中学校区には、山田・東山田・北山田の3つの小学校があり、1つのコミュニティとして連携が進められており、まちのマスコットキャラクター「やまたろう」を活用して、さまざまな取組が行われています。4つの小中学校とPTA、町内会や地域行事を記載したコミュニティカレンダーを作成・配布したり、学校と地域をつなぐホームページ「やまたろうネット」の運営、学校の授業支援や校外行事の引率等のボランティアのコーディネートを行っています。生徒たちも、地域のお祭りの手伝いなどのボランティア活動や地域行事へ参加するなど、地域で活動しています。生徒たちは、教師以外の大人と話をしたり、話を聞く機会が増えたことから、落ち着いた学校生活の維持やコミュニケーション能力の向上につながり、また、教職員も、多くの人の関わりが意識改革となり、意欲的に活動するようになり、学校の活性化につながっているとのことです。
同校では、多くの人が学校づくりに参画することで学校への関心が高まり、それが学校を中心とするコミュニティの構築、さらには、まちづくりにつながると考えているとのことです。
東山田中学校と同校コミュニティハウスは、今後も学校と地域をむすぶ取組をより一層推進していきたいとのことでした。
主な質疑
- 地域ボランティアによる生徒の面接について
- 住民の抵抗感について
- コミュニティハウスと学校運営協議会との関係について
- コミュニティハウスの夜間利用体制について
- 学校運営協議会の委員について など


概要説明を聴取した後、施設を視察
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校(神奈川県横浜市)
サイエンスエリートを育成するための取組について
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校は、神奈川県内初の理数科高校で、横浜市の全市立学校における教育改革のパイオニア校に位置づけ、横浜開港150周年、横浜市制120周年の平成21年4月に開校しました。
同校は、「日本の将来を支える論理的な思考力と鋭敏な感性を育み、先端的な科学の知識・技術、技能を活用して、世界で幅広く活躍する人間を育成する」ことを教育理念とし、「驚きと感動」による「知の探究」による人材育成を目指しています。
同校の主な特徴の1つに、スーパーアドバイザーの参画があります。和田昭允氏(東京大学名誉教授、理化学研究所研究顧問)が常任スーパーアドバイザーに就任されるなど、先端科学研究分野において優れた功績を有する5人がスーパーアドバイザーとして参画し、教育方法などについて指導助言を行っています。また、科学技術顧問として、50人を超える大学・大学院や企業の研究者等、外部専門家が研究指導や実験指導を行っています。その他、理化学研究所横浜研究所や海洋研究開発機構等、研究機関との連携により、生徒が研究施設を訪問したり、研究所からの講師派遣を受けたり、慶應義塾大学や横浜国立大学、横浜市立大学など大学との連携により、高校から大学に通じる教育内容等の研究や大学との連携講座を実施しているとのことです。
また、同校は、平成22 年度にスーパー・サイエンス・ハイスクール(SSH)、同27年度に再びSSHに、同26 年度にはスーパー・グローバル・ハイスクール(SGH)の指定を文部科学省から受け、同校オリジナルの課題探求型の授業「サイエンスリテラシー」など、特色ある教育活動を進めており、「知識と知恵のサイクルの学び」を体感した同校の生徒たちは、国際科学技術コンテストや研究発表等での活躍とともに自らの高い進路希望を実現し、各方面から高い評価を得ています。
横浜市教育委員会により進学指導重点校にも指定されており、平成29年4月には、同校に附属中学校を併設し中高一貫教育を導入する予定です。
横浜サイエンスフロンティア高校としては、今後も、文理の枠を超えたサイエンス教育の一層の充実を図り、将来のグローバル人材の育成に努めていきたいとのことでした。
主な質疑
- サイエンスに触れる機会の海外との比較について
- 早期に理数系に絞ることによる弊害について
- 就職状況について
- 飛び級に対する見解について
- 1日のカリキュラムについて など


概要説明を聴取した後、校内の主な施設を視察
お問い合わせ
京都府議会事務局委員会課調査係
京都市上京区下立売通新町西入
電話番号:075-414-5541
ファックス:075-441-8398