サンショウモ科
サンショウモ
Salvinia natans (L.) All.
| 京都府カテゴリー | 絶滅寸前種 |
|---|---|
| 2002年版 | 絶滅寸前種 2002年版を参照する |
| 環境省カテゴリー | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) |
| 近畿レッドデータブックカテゴリー | 絶滅危惧種C |

| 選定理由 | 昭和40年代以降激減し、府内の残存数はわずかである。現在は丹後地域に見られるだけになっている。 |
|---|---|
| 形態 | 浮遊する水草で、冬枯れする一年草。茎は伸張し、葉を対生状に付ける。それとほぼ同位置に水中に伸びる茎状器官があり、一部は根状、一部は胞子嚢となる。葉の表面には微細な突起が多生し、水をはじく。胞子には大小二型あり、秋に熟し春に発芽する。 ◎参照 日本の野生植物 シダ(平凡社)284、原色日本羊歯植物図鑑(保育社)171 & 253 |
| 分布 | 本州、四国、九州、朝鮮半島、中国大陸、台湾、インド北部、ヨーロッパ、北アメリカ。 ◎府内の分布記録区域 丹後地域、京都市域(絶滅)、山城地域(絶滅に近いが、現状不明)。 |
| 生存に対する脅威 | 水田への除草剤の使用、水の富栄養化。 |
| 必要な保全対策 | 上記の原因を排除する。人工栽培は比較的容易なので、自生地を復元することも可能である。 |
| 特記事項 | 土を掘り返すと、休眠胞子が発芽することがあるので、注意が必要である。 |
執筆者 光田重幸
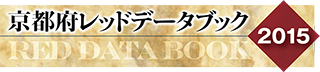
.gif)