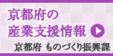ここから本文です。
株式会社MOLFEX(京都企業紹介)
知恵の経営、元気印、経営革新、チャレンジ・バイの各認定等を受けた中小企業を紹介するページです。
振電相互作用密度理論により企業の新材料開発をサポート
(2024年3月18日、ものづくり振興課 足利・坂井)

株式会社MOLFEX(2018年設立、京都大学福井謙一記念研究センター内)(外部リンク)の佐藤共同創業者(京都大学福井謙一記念研究センター センター長、教授)と上島代表取締役CTOにお話をおうかがいしました。
物性や化学反応を支配する振電相互作用
--振電相互作用密度理論による独自の分子設計技術で、大手企業等の材料開発サポートを行ってらっしゃる会社だと聞き、「これまで聞いたことないビジネスだ、ぜひお話をお聞きしたい!」と思ってやってきたのですが・・・、そもそも「振電相互作用」って何ですか?
佐藤)分子の中の電子と分子振動の間の相互作用のことです。例えば、分子に光が当たると、電子が外側の軌道にジャンプして、励起状態になります。そして、熱エネルギーを放出し、その際には振動を引き起こして元に戻ります。時には熱エネルギーではなく発光することもあります。
--ふむ。
佐藤)電気抵抗の正体もこの振動です。あるいは、この振動(正の電荷)によってクーパー対(電子が対を組んでいる状態)が形成され超伝導を引き起こすなど、振電相互作用は、発光性、電気伝導性、超伝導性、強誘電性、磁性などの物性や化学反応を支配する基本的な相互作用なのです。

分子設計を「経験」から「論理」に変える振電相互作用密度理論
--そうなのですね。なのに、御社のような会社は珍しいのは、なぜなのですか?
佐藤)学生の時に、化学反応の計算はされるけれども、どういう分子の場合にそうした化学反応が起こるのか分かっていないと思ったんです。そして、様々な化学反応の原因に振電相互作用が影響しているなと気付いたんです。
--どうして他の人たちは気付かなかったのでしょうか。
佐藤)こういう物理化学の分野に、振電相互作用は出てこなかったのです。他の理論が主流であったためです。
--そうなのですね。
佐藤)私は、電子と分子振動の相互作用を記述できる「振電相互作用密度理論」を開発しました。これまでの分子設計手法は、経験に基づいたものでしたが、これにより、理論・計算による論理的な材料設計が可能となります。
精密分析・設計により新材料開発のスピード化・低コスト化をサポート
--ほう。
佐藤)こうして振電相互作用をコントロールすることで、例えば、発光分子の発光効率を向上させることもできます。Anthraceneの発光効率30%です。振電相互作用密度理論によれば、分子のどこでどういう反応が起こっているかが分かるのです。それが分かれば、どこを改良してやればいいかが分かり、発光効率96%の材料を開発することができます。
--おお!
佐藤)このように、振電相互作用密度理論によって、様々な機能の発現や反応性を制御する設計指針を与え、精密な分子設計を実現することができます。これをサービス化した世界でも珍しい会社なのです。
--すごいですね。
上島)顧客は、大手材料メーカーが中心ですが、例えば京都にも多い染色関係などの中小企業さんもサポートできると思っています。新材料の開発を、速く、低コストで実現できます。
まるで魔術なサイエンス
--ところで、ここは日本初のノーベル化学賞を受賞された福井謙一先生の名前を冠するセンターですね。
佐藤)物質を構成する電子が原子核の周りを軌道を描いて運動するという量子論の考え方を基に、物質が化学反応を起こす際の電子の役割を「フロンティア電子軌道理論」という形で説明されました。

--そうなのですね。
佐藤)ただ、分子量が大きい場合に、説明がつかなくなることがあったのです。福井先生も最後まで気にされていたと思います。振電相互作用密度理論では、どこでどういう反応が起こるか予測できるようになりました。
--ほう!すごいですね。
佐藤)例えば、色のスペクタクルの構造をしっかり示すことなんかもできます。「こんな色の分子を作りたい」といったことにも対応できますよ。
--まるで魔術ですね。
佐藤)いえ、サイエンスです!
ぜひ材料開発をなさっている企業の皆様、同社を頼ってみてはいかがでしょうか!
お問い合わせ