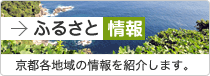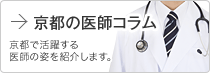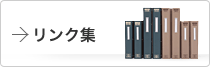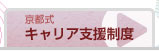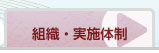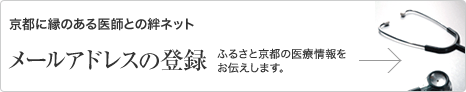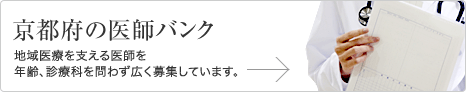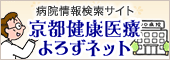京都で働きたい医師・医学生の方へ 京都で暮らし、京都で築くメディカルキャリア
KMCC地域医療フォーラム ~地域の病院と診療所、訪問看護ステーションの取組~
パネルディスカッション
Chapter2
地域の中核病院 診療所との連携や取り組みについて
司会者それでは、まず初めに、川島先生に地域の中核病院からの御発表として、地域中核病院と医師会の先生方との連携を中心に、御意見、御感想などをいただければと思います。

福知山市民病院 総合内科医長 川島 篤志氏
日本の医療については、多くの場合、大学病院や都市部の大病院での医療、もしくは極端な医療過疎地域の医療がメディアを通じて報道され、福知山や久美浜のような、地方の医療の状況が報道されることが少ない印象を受けます。
地域の医療を支える観点で言えば、地域中核病院がしっかりしていないと、診療所の先生方だけでなく地域の住民の方々の安心が担保できないと思っています。全体的な医師不足・看護師不足の中で、地域中核病院がどのような形で地域の安心を提供できるかと言えば、救急医療と入院医療、そして常識的な範囲での高度医療だと思います。
これらを実現していくためには、医師としてのマンパワーが必要になってきます。限られた医師数の中でどのように院内で機能分化するか、また診療所の先生方との役割分担とその窓口をどのように担っていくかが大事だと思っています。
現時点で、福知山で4年間勤務していますが、地域医療の視点において当院の環境面で感謝していることは、香川 惠造院長が当地で長期間在籍されていることです。このことによって、診療所の先生方と地域中核病院のトップの先生が密に連絡を取られ信頼関係を築きあげていること、そして、定期的な福知山医師会との勉強会など、病院の医師と診療所の先生方との顔の見える関係ができていることにあります。
何年間毎という周期で、大学病院から先生方が派遣されている科があります。その比較的短い間では太いパイプというところまでは行かないかもしれないけれど、軸になる人がおられたり、継続性があったりすれば、常にパイプは保たれます。高度な医療を提供できる、救急医療を提供できる医療機関であるという観点から、大学から医師を派遣していただけるのも、ありがたいことだと思います。
2~3年間で医師が替わられること、もしくは外来のみ診療を行う非常勤医師のことを残念に思う住民の声も、ときどきお聴きします。ただ地域の中核病院として救急医療と入院医療、そして高度医療を提供するためには、それなりの循環はあって然るべきと思いますし、地域の先生方とのパイプを中核病院がしっかり持っていることこそが、地域の安心に繋がる医療の提供の源になるのではないかと思います。こういう点をご理解いただければと思っています。
中核病院では、救急医療を常識的な程度の高度医療で提供し、入院医療もしっかり提供できるということ、そして、医師会の先生方との連携が不可欠というお話でした。福知山では、そこがうまく行っているというお話でしたが、続きまして、髙尾先生から、診療所からの御意見をお願いいたします。

福知山医師会会長 髙尾 嘉興氏
この地域では、病院と開業医の病診連携、または病院と病院の病病連携が非常にうまく行っており、それは香川先生の姿勢、理念と、医師会、そしてもう1つの急性期病院、このトライアングルの関係が非常にうまく行っているからだと思っています。
唯一不満があるとすれば、満床という状態が続く場合もあるので、何とか解消できるように総力を発揮していただき、さらに充実すれば、この地域がより良くなるのではないかと思います。
医師の確保に関しましても、本日、市長が出席されておられますので、あえて言わせていただきますが、京都縦貫自動車道が福知山に来なかったのは重ね重ね残念だと思っています。
京都市内から医師が来るのに、丹波IC(船井郡京丹波町須地)で降りて、追い越し禁止の国道9号線を長時間走ってくるのは非常に疲れます。一生懸命患者さんを診た後で京都市内に帰るにしても、丹波ICまで長時間掛けて行かなくてはならないのです。
市長にいつも言っていますが、福知山市の政治家にそれをやっていただかないと、医療に携わっている人間は、地域の医療を最高のものにしようと必死に頑張っても、交通アクセスが悪いというようなことでスタッフも集まらないのです。
福知山市民病院に関しては、医療連携室が院長の指導で対応が非常に素晴らしいです。電話での診察予約も非常にスムーズです。ごくまれに満床で入院できないとか、予約をしないとすぐに検査を受けられない場合があるので、緊急を要する時には、より一層しっかり対応していただいたらと思います
。
後は、病院受診後の結果はすぐにファックスをいただいていますし、途中経過や退院後のサマリーも迅速に送付していただいており、病院連携がうまく行っていることの証だと思っています。
福知山は現在、病診連携がたいへんうまく行っているとのお話でした。それでは次に、地元に住んでおられ、医療サービスを受ける、住民としての立場から、谷垣様から御意見等をお願いいたします。

保健師・助産師 谷垣 英美子氏
福知山市民がどうようなニーズを持っているか、私なりに考えて参りました。
市民は、日常的に風邪や慢性疾患を持っている場合は、開業医の先生に行かれることが多いので、まずは診療所・家庭医が確保できているかになります。ただ、高齢人口が増えることによって、これから必要な在宅介護、往診、看取りをしていただける家庭医がいるかどうかが大事なことだと思っています。市民というのは、総合病院志向というか、症状によってあちこちの専門医に行くことがあり、そこで検査や高度医療を受けて、その診断が一番だという考えがあります。
この北部でも、専門診療科を求めて京都市内とか、大阪、神戸へと高速があれば、そこまで行くという現状が、まだまだあります。しかし、市民にとって遠くに行くことは御家族にも負担が掛かり、最終的には地元に帰りたいので、地元に入院施設や福祉施設があるかどうかが大きな問題だと思っております。
遠くへ行っても帰ることができる、紹介されて戻ることができるシステムが、今後は大事になってくると思います。
それから、やはり救急医療体制が整っているか、少し古い話題だとSARS問題、最近だと新型インフルエンザの時に、地元で地域医療を支える健康危機管理は、中核病院だけでなく、開業医の先生方を含めて全体で担っていくべきで、大事にしないといけない部分ではないかと思います。
医療が専門分野化される中で、住民から「こういう症状の時は、どこの医療機関に行ったらいいか」、「専門医はどこなのか」ということをよく聞かれます。これからは、症状から、明らかにどこの科を受診して良いか分からない場合などでは、総合医・総合診療医が期待されているのではないかと思います。
また、20年ほど前は、小児科の診療所は福知山にはなかったのですが、今では2診療所と2病院に、小児科があります。
医師数は増えてきてはいますが、まだ小児科医の数は少なく、小児科医の先生の負担が大きいです。住民のコンビニ受診の問題など、地域が病院を支える体制を真剣に考えなくてはとも思います。
心配なことは、出産できる産婦人科が減ってきていることです。このままだと、市内で安心して産める病院は市民病院だけになってしまうのではないかと心配しています。
整形外科の先生も不足しているようで、市民にとって安心して受けられる医療体制については、市民も一緒になって考えていかなければいけないなと思いました。
市民の立場から、危機管理、看取りといったいろんな局面で、御意見、御希望をいただきました。
次のテーマは、「訪問看護、在宅医療の取組」です。
訪問看護、在宅医療の取り組み
司会者先ほど、京丹後市のお二方から訪問看護ステーションの取組について、御報告いただきましたが、発表に関して、あるいは、在宅医療の取組や訪問看護との連携などについて、パネリストの先生方から御意見をいただきたいと思います。まず、髙尾先生からお願いいたします。

福知山医師会会長 髙尾 嘉興氏
在宅医療での訪問看護は必須です。看取りは、最期をどこで迎えるか、本人の人生観の問題であり、自分が生まれて育った家で死にたいという場合になります。
また、胃瘻で一番問題なのは誤嚥性肺炎を繰り返すことです。受診して入院、良くなれば退院ということを3回も繰り返すと「胃瘻しかない」と伝えますが、御家族からは「胃瘻は結構です」という話にもなります。そういう場合に患者さんはどんな気持ちなのだろうかと思います。
口から食べるところを、直接胃に穴を空けられて栄養を注入されて長生きするということが本当に幸せと言えるのか、いつも気になっています。医者の立場から言うと、「何もしなくて結構」と言われるのは非常に辛い部分があります。
ところで、診療所に来られる患者さんで、そんなに認知症は進んでいないように感じる時があるのに、御家族や周囲の方から見ると問題行動が非常に多いというケースがありますが、病院側から見てどのように思われますか。

福知山市民病院 総合内科医長 川島 篤志氏
急性期病院に勤める医療者のスタンスにも、若干の問題があるようにも思います。
今までの医療は治る人を診てきた歴史があります。そのため、医療者には「治して帰す」、患者さん側も「治って帰る」という認識がありますが、高齢化社会を迎え、「治りにくくなっている(元には戻らない)」、「治るのに時間がかかる」、「ほとんど治らない」という人が増えてきているのが現状です。このことが急性期病院の医者や看護師には十分浸透していない印象です。
また老年医療の考え方を医療者だけでなく、患者さん・ご家族にも持ってもらうことが必要になってきます。
入院することで、認知症が進行する方や、さらに機能が落ちる方が増えてしまうことはデータとしても分かっています。それをどこまで「治す」かです。
例えば認知症の薬というものがありますが、基本的にアルツハイマー型認知症を含めて病気自体は治りません。進行する病気であると伝え、何らかの薬を処方する際に、いかにその時点でのご本人さんの意見を聞いておくかということが重要な問題になります。また家族の方にも伝えることも必要です。
急性期病院で診療を行っていて感じることですが、自分のご両親がどんな病気になっているか、を理解できているご子息が、意外と少ないように思います。
病状説明は悪くなった時に行くもの、ということがあるかもしれないですが、非悪性疾患でも進行性疾患に罹患した際や、単純に1年に1回の御両親の受診に付き添って病院に行って病状を認識するなど、悪くなる前から病態を知ってもらう、また将来的に訪れる死に対する死生観を検討することが必要になってくると思います。なかなか実行は難しいことかもしれませんが、適切な医療情報を共有すること・検討することが、今の社会には求められると思います。
また、これらのことを、急性期病院の比較的若い医師が十分わかっていない可能性もあります。ただ、今の福知山市民病院には、家庭医療のトレーニングを積んできた医師が複数名います。急性期の病院であっても、病気だけでなく、家庭背景・社会背景までを診る意識を持った医師が増えることによって、地域の医療は変わってくると思います。
また地域での急性期医療は、前述したように救急医療・入院医療、そして高度医療と思いますが、それだけに特化しきれないのが、今の問題だと思います。なかなか退院できない患者さんを抱えながら、新たな入院患者さん用のベッドをどう確保するか? 看護師の数も十分ではない中で、決まった数の患者さんしか診ることができない現状が、なぜ起きるか? 医療を受ける人と提供する人の価値観が違うなかで、何かを押し付けることはできません。
しかし、患者さんや国民の考え方の変化、また看護師の労働環境・医師の労働環境などの改善など、取り組まないといけない問題がだんだんと難しくなってきているという認識を、共有しないと来たる2035年には厳しくなっているのではないかと思います。
在宅での看取りは、福知山地域では当院としてはやっていないので、基本的に診療所との連携になると思います。ただ、診療所の先生方も激務だと思いますし、24時間のチームが組めるかというと難しいのではないかと思います。
地域や先生方の考え方や体力面もありますので、福知山地域でも議論していかなくてはと、個人的には思っているところです。しかし、院内の体制を整えることが第一であり、急性期病院からでも家族背景・社会背景のことを考えるような医療を展開できるように少しずつ変えていければと思います。
自分自身は定期的に受診される予約外来枠を持っているので、その中で家族背景も含めた話ができるような医療を実践しているつもりではあります。
病院の立場に加えて、川島先生からは、高齢化が進んでいく中で、治りにくくなっている患者さんが増えてきているとか、在宅の受け入れなど、難しいということで、国民の方でも考えていただくことがあるのでは、という御意見をいただきました。川島先生のお話や、訪問看護ステーションや在宅医療のお話で、何か御意見ありましたら、谷垣様からお願いいたします。

保健師・助産師 谷垣 英美子氏
家庭において死を看取るというのが怖い、どうしていいか分からないという気持ちがあると思います。
私事ですが、この2年でアルツハイマーの母と要介護の父を見送った中で、父は最後まで「家に帰りたい」と言っており、帰してあげたいという家族の気持ちがあっても、死を看取るための往診や訪問看護スタッフ、ケアマネ―ジャーさんや関係者の体制がなく、病院で亡くなりました。これからの福知山市でも、北部でも、医師がなかなか増えない中で、家族がどう支えていくかが重要になっていくのではないかと痛感しています。
谷垣さんの御経験から、家庭で最期を看取るには、その地域での体制によっては、難しい場合もあるということでした。先ほどの御報告から、京丹後市では、地域の体制が進んでいるという状況でしょうか。

京丹後市立弥栄病院 訪問看護ステーション管理者 森岡 絹恵氏
当院では訪問診療をしている先生が2人おり、医師が少ない中で、1人の医師にかかる負担は大きいですが、訪問診療をがんばっていただいています。
看取りに関しても、御家族を含めて、医師の方から在宅で看取りましょうという話をして、チーム医療で体制を整えていることを伝えた上で、在宅で看取るケースは何件かあります。ただ、在宅医療に興味のある医師の下では訪問診療の幅が広がりますが、そうでない医師の下の在宅医療だと活気がなくなっていくように思います。個人的には、在宅医療が、常に同じようなシステムで、皆が受けられるような体制ができたらといつも思っています。
ただ、在宅医療に興味のある医師の下では訪問診療の幅が広がりますが、そうでない医師の下の在宅医療だと活気がなくなっていくように思います。
個人的には、在宅医療が、常に同じようなシステムで、皆が受けられるような体制ができたらといつも思っています。

京丹後市久美浜病院 訪問看護ステーション管理者 小森 弘子氏
当院の訪問診療会議では、在宅の看取りに取り組むことで一致団結しております。
看取りができない一番の問題は、介護力の問題だと思います。京丹後市も1人世帯や老老世帯がずいぶん増えており、介護力不足のために、本来ならば在宅で安らかに見送ることができるはずの方もたくさんおられます。そこが地域の大きな課題かなと思っています。

福知山医師会会長 髙尾 嘉興氏
看取りとは最期をどう迎えるかですが、在院日数を少なくするために早期に退院し、在宅で治療するとなると、やはり家族に非常に負担がかかります。その際に、訪問看護やヘルパーやケアマネージャーに世話をしてもらえると非常にうまくいくと思います。ただし、独居老人や老老介護、さらには認認介護(どちらも認知症)の場合だと、服薬管理もむずかしくなります。
先ほど、訪問診療を行う際に、医師のやる気があるかないかという話は、胸に響きました。私も若い頃は、1日に8件ほど往診に行ったりしていたのですが、最近では、往診は急患ぐらいしか対応できなくなってしまいました。
また、パーキンソンで寝たきりの患者さんを診ていたことがありました。褥瘡予防のために体位変換は2時間置きにしてくださいと伝え、まだ御主人がお元気だった頃は、きちんとされておりましたが、1年ほど経つと「私は疲れた」と言われたケースがありました。
みなさま、ありがとうございました。
これまで、1つ目のテーマで、病診連携、2つ目のテーマでは、訪問看護ステーションや在宅医療について、ディスカッションしていただきました。
本日は、せっかくの機会ですので、会場にお越しの皆様の中で、御質問や御意見がありましたら、お受けしたいと思います。
Chapter3
● 意見交換● 総 括