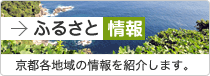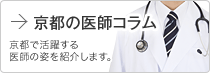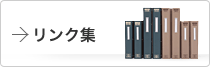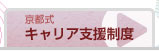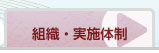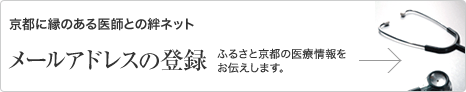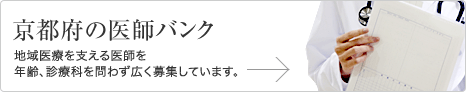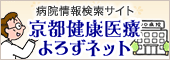京都で働きたい医師・医学生の方へ 京都で暮らし、京都で築くメディカルキャリア
KMCC地域医療フォーラム ~地域の病院と診療所、訪問看護ステーションの取組~
パネルディスカッション
Chapter3
意見交換




司会者
本日は、せっかくの機会ですので、会場にお越しの皆様の中で、御質問や御意見がありましたら、お受けしたいと思います。

京丹後市立久美浜病院 病院長 赤木 重典氏
東京の医療環境を基に医療政策が展開されているのが、問題だと思います。
三次救急が隣立する東京に比べると、片や京丹後は、500平方キロの広大な敷地に十数人の開業医しかおられません。われわれ京丹後の4病院としては、開業医の先生方には、夜間土日はゆっくりしていただき、その代わりに長い間開業していただいて、仕事しやすい環境ということで、例えば御子息が医者になられたら帰ってきてもらうような環境づくりを今進めています。
つい20年前まで、京丹後には小児科医は居ませんでした。その後で1人の小児科医が派遣されるのをきっかけに、「子どもは事故以外ではほとんど死にません。口から水分を取っておしっこが出ていれば大丈夫。」という久美浜病院内の合意の下で、20数年、京丹後では小児科医を支えてきました。外科医や内科医や整形外科医など全ての科の医者が小児を診ています。
何かあればバックにいる小児科医に連絡して指示を仰ぎ、年に数回ですが、緊急時には、小児科医が出てきて診察を行うというシステムです。私は、100の地域があれば100の地域医療のあり方があると思っています。
そのためには、その地域で一人一人何ができるか、何をしなくてはいけないか、という思考を常々繰り返すことが必要だと思います。
看取りに関しては、押しつけることは全くなく、最期を迎える場所を選ぶ時に、在宅での看取りが選択肢の一つとしてあるという環境を整備することが、われわれ病院や行政の責任であると思っています。
福知山市がこれだけ充足されていても、患者さんの要求は恐らくもっと高いところにあり、そこは行政の責任であり、われわれは精一杯努力するしかないと思っています。
訪問診療をもっと広めるためには、一人が出張などで留守にする際に、他の医者が代理をして助け合うという横の繋がりと協働がキーワードになると思います。 そういった中で地域医療は展開していくべきものだと思っています。
司会者
ありがとうございました。久美浜で、本当に地域に合った形で、工夫を凝らして活動されているということでした。
そのほかに、御質問や御意見ありましたら、お願いします。

京丹後市立弥栄病院 内科医長 堀口 正樹氏
本日は、在宅での看取りがテーマとなっている中で、私自身が医療のテーマとして取り組んでいる、「死の質(quality of death)」について、香川先生のお話もあり、大変勉強になりました。
訪問看護ステーションから見て、それぞれの診療所の先生や中核病院の医師に対して、「これがあったらできるのに」と思うことがあれば、教えていただけませんか。

京丹後市立弥栄病院 訪問看護ステーション管理者 森岡 絹恵氏
私は今年の4月から訪問看護に入りましたが、病棟での経験が30年近くあり、訪問看護に移って在宅で生活されている利用者さんの状況を拝見すると、病院でも難しいのではと思うような状態の方が、多数おられる現状があり、驚きでした。
また、研修医の先生とお話をした時に、訪問看護をどう依頼したらいいのかということすら知らない方がおられましたので、訪問看護のシステムをよく知っていただけたらと思います。

京丹後市久美浜病院 訪問看護ステーション管理者 小森 弘子氏
特に、開業医の先生にお伝えしたいのですが、訪問看護ステーションをもっと利用していただいたら、先生方がもっと楽になると思います。敷居は全く高くないので、気軽に連絡していただければ、すぐに伺います。
在宅ターミナルなどは、お医者さんが頻繁に出向かなくても、主治医とのコミュニケーションや連携が、できていれば、日々のケアに関しては、訪問看護ステーションを利用していただければと思います。

福知山市民病院 総合内科医長 川島 篤志氏
在宅看取りがオプションにあるという感覚を、急性期にいる医療従事者が持つことと、そういうオプションがあることを一般住民の方も少しずつ情報共有することが、一つのポイントだと思います。
また、私たちの病院の中で難しいと感じることは、急病に直面した患者さんと御家族からの信頼を、短期間で得ることです。しかも、まだ人生経験も少なく、付き合いも短い、若い医師がどこまでできるのか、ということです。やはり、普段から診られている診療所のベテランの先生方が、生活観や社会背景を把握され、長期間培ってきた信頼関係のもと、死生観などを共有することが重要かと思います。短期間で信頼関係ができていない中での在宅医療の推進はなかなか難しいと思っています。
後は、それぞれの地域のマンパワーや施設の有無にかかってくると思いますが、まずは、医療機関や、国民の中で情報共有が必要だと考えます。
司会者
いろいろと御意見をいただき、どうもありがとうございました。
最後に、香川先生に全体の総括をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
総 括

市立福知山市民病院 院長 香川 惠造氏
厚生労働省が行った「どういう場所で死を迎えたいか」というアンケートによると、日本国民の8~9割近くが「自宅で迎えたい」ということですが、現実には、家族に迷惑が掛かるから、なかなか難しいという理由などで、結果的に病院で亡くなる方が多いという現状です。
ある大学の産婦人科の教授が非常に興味のある話をされていました。
「65歳で定年と言われていますが、僕らにはその後も働き口はありますよ。」と言われるので、どういうことかお聞きすると、「お産は夜間が多いのですが、女性医師が増えるなど、夜中のお産をやる人材が少なくなっているので、自分はリタイヤしても夜中のお産専用の医師として生きていくことができる、だから、職はあるのです。」こういうお話でした。
訪問看護ステーションの小森さんが言われたことで、非常に心強いなと思ったのは、「もっともっとステーションを利用してほしい。ただ看取りの最期の瞬間は医師が必要です。」という言葉です。最期の臨終を告げる看取り医がいれば、在宅で対応できる数は増えると思いますし、私も「看取り医」をやってもいいなと思っています。
私のおじいさんの時代には、医師はあらゆることをやっており、在宅医療を担うのは当たり前でした。
福知山市の人口動態をみますと、生産者人口の低下を補う意味では住民は75歳まで働かないと補えません。地方都市の開業医の平均年齢は年々上がっているというデータもあります。開業医の先生も80歳まで働いていただき、80歳過ぎには看取り医になっていただければと思います。
弥栄病院の安原先生がおっしゃったように、長期に渡るケアは、生活に根ざした介護と医療を一体化したシステムが、社会としてこれから必要ではないかと思います。
また、久美浜病院の赤木先生がおっしゃったように、福知山は福知山の、久美浜は久美浜の、それぞれの地域をチームとして解決していくことが必要ではないかと思いました。