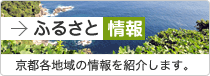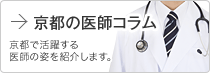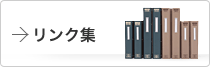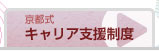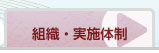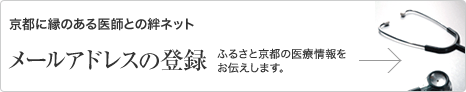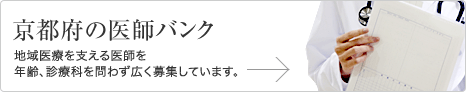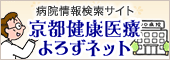京都で働きたい医師・医学生の方へ 京都で暮らし、京都で築くメディカルキャリア
KMCC(Kyoto Medical Career support Center)開設記念フォーラム
京都のスーパーGeneralists集合!
洛和会音羽病院 総合診療科兼感染症科部長 神谷 亨先生
都市型病院におけるジェネラリストの育成
都市型の「総合診療医の育成」についてご紹介をします。
総合診療医のニーズとは、次のように考えています。医療が高度化し、専門分化していく中で専門医が育成されてきました。しかし、複数の疾患を抱える高齢者が増加する中、専門医の力を合計するだけでは対処困難な事態が増えていくように思います。内科系疾患全般に常に目を配っている医師が、ある一定の割合で存在した方がいいだろうと考えています。
洛和会音羽病院は京都市山科区に位置し、病床数588床のケアミックス型病院です。一般病床は428床で、「医療療養型病床」「回復期リハビリ病床」「認知症病棟」を有しています。2011年10月にはPET‐CTとリニアックを導入し、小児科、婦人科のアメニティを充実させた新棟がオープンしました。
当院総合診療科は内科系11診療科の中の1つであり、38全診療科の中でも最大の診療科となっています。
総合診療科のスタッフ数は現在合計14名です。総合内科、家庭医療、膠原病、感染症、救急医療、ICU、疫学等、様々な分野に興味を持ったドクターが集まって切磋琢磨しています。現在シニアレジデントは各学年3名、合計9名です。
当科のミッションは、「総合内科の診療」および「総合医の育成」を通じて社会に貢献することです。
内科の「ジェネラルな力」はどのようにして身につくのか?
内科系を中心とした様々な疾患に出会い、それらを様々な場(外来、一般病棟、ICU、ER、老健施設、往診等)で経験することが必要です。また、診療内容について他の医師とディスカッションすることで、自分自身の医療行為が標準的であるかどうかチェックができる環境に身を置くことも大切です。
当科の2010年の入院患者数は、合計1,262名でした。当科に入院する患者の75%がERからの入院でした。また、当院にERから入院する患者の約4分の1が総合診療科に入院となっています。例えば、不安定狭心症等でERに搬送された患者は心臓内科に入院、急性期の脳卒中は神経内科に入院となりますが、複数の疾患を抱えていて内科系専門科に振り分けることが困難な患者は総合診療科に入院となります。高齢者の誤嚥性肺炎、尿路感染症などが主たる守備範囲となりますが、約半数以上を占める「その他」の疾患領域にバラエティに富んだ疾患が存在します。
不明熱に始まり、特異な感染症、まれな膠原病などが含まれます。また、フィリピンから帰国した患者の狂犬病を経験したこともあります。このような様々な疾患を診察することで「総合医」を教育しようとしています。
教育方針は…
①まず最も大切なことは、「知識の共有」、シェアしようという風土です。自分の頭の中だけで考えるのではなく、学んだことを下級医へ、また上級医に紹介することが大切です。人に教えることで「自分もさらに学ぶ」ことが出来ます。
②「屋根瓦教育」を行います。年齢の近い医師からのアドバイスを受けることが出来ます。
③総合診療科の入院患者さんには疾患の偏りがある程度存在しますので、様々な疾患を経験するためにも自分の強化したい専門科にローテートができるように配慮します。
④日本あるいは世界レベルでの標準的な診療を行っているかどうか、エビデンスやガイドラインに則った診療を行うように心がけています。
⑤検査がすぐにできない往診等の診療では「問診」と「身体所見」を重視した鑑別診断能力が不可欠です。総合診療医としての「診断推論能力」
の向上を目指します。
問題解決能力、医療の諸問題への理解
いくら医療が高度化しても、まだ解明されていない問題点は次から次へと出てきます。これらの問題点をどのように解決していくのか、どうやって調べていくのか、誰に尋ねればわかるのかなど、下級医は上級医の行動を見ることで学習します。この能力は一人前の医師として地域診療にあたった際、解らない問題が発生しても、自分自身の力で解決出来る力となります。
また、現代医療の抱える様々な問題、例えば高齢者の一人暮らしの増加や、老老介護の実態、終末期医療といった問題に関心を持ち、それを「総合医」としてどう解決していったらよいのかについて議論する場を設けるようにしています。
その他、患者、家族、多職種の方々との「コミュニケーション能力の向上」、「人格の向上」に関しても積極的に取り組むように指導しています。
都市型病院におけるジェネラリストとは?
何よりも当院のような専門医がいる病院で総合医を育成しようとする時に大事なのが、専門医との良好な協力関係の構築です。このためにはコミュニケーション能力、人格の向上が欠かせません。さらに、「ジェネラリスト」は、個々の患者において最良の成果を出すために、「自分がどこまで診療可能か」という守備範囲を見極めることも大切です。
ジェネラルな力を育成する研修内容
総合診療科は、80~90名の入院患者を担当しています。これらの入院患者を3チームで診療し、1チームは、スタッフ2名、後期研修医1~2名、初期研修1名の合計4~5名で構成されています。常時1チームが25~30名の入院患者を担当しています。
研修医の一日をご紹介します。
毎朝8時よりレクチャーが30分あり、その後8時30分から病棟回診をチーム毎に行います。
朝の回診では、スタッフレベルの医師が研修医のプレゼンテーションを聞き、夜どういう変化があったのか?今日はどういう治療方針・検査方針なのか?等を適宜チェックします。回診時に、問診や身体所見をチーム全員で実施することで、「問診」「身体所見」を重視したディスカッションを行います。
ランチタイムには「症例カンファレンス」があります。毎回1例ずつ、思考過程と診断推論を重視したディスカッションを行っています。
夕方には各チーム毎に1日の終わりのカンファレンスを行います。その日の患者の状態把握、検査結果の確認や、今後の検査・治療計画の確認を行っています。
当院では米国の医科大学から総合内科系教授陣を「大リーガー医」として招聘し、スタッフと研修医の教育を行っています。年間数名の「大リーガー医」を招いており、一人の「大リーガー医」は2~3週間滞在します。「大リーガー医」滞在中は、ランチタイムカンファレンスや夕方のレクチャーは英語で行います。
その他各種カンファレンスがあり、学べる機会を十二分に用意しています。
10年以上の歴史のある「GIMカンファレンス」は非常に好評で、月1回の開催時には兵庫県、大阪府、遠くは長野県と各地より毎回50名を超える医師が参加します。毎回診断に苦慮した3症例が提示され、「診断推論のトレーニングの場」として大切なカンファレンスとなっています。
また、音羽病院と姉妹病院である丸太町病院と毎月1回合同で開催している「音丸カンファレンス」では、学びの多かった症例を1例ずつ提示して活発なディスカッションを行っています。
日本内科学会認定医・総合内科専門医、日本プライマリケア連合学会認定医等の取得、各種学会での発表、論文執筆などについても積極的に取り組むように指導しています。
将来内科系の何れの科に進むにしても、内科の「ジェネラルな力」は必要です。3年から4年間「ジェネラルな診療」を経験した後で、家庭医療に進んだり、内科系専門科に進むという道もあるでしょう。また専門領域をサブスペシャリティとしながらも、再び「病院総合医」の道を歩む、といった私のような医師も出てくるのではないかと期待しています。
最後に、来年度(2012年)以降の新しい試みを紹介します。
後期研修を終了した卒後6年目以上の医師を対象として「病院総合医フェローシップ」という研修プログラムを開始します。後期研修時に専門分野での診療をした医師で、もう一度「内科全般」を勉強し直したいと希望する医師、或いは「家庭医療」に進む前に病院総合医を一定期間経験したい、また開業前に内科全般のトレーニングを受けたい、といった様々な医師のニーズに答えたいと考えております。詳しくはホームページをご覧頂きたいと思います。
洛和会音羽病院ホームページ 総合診療科 シニアレジデントのページ
http://www.rakuwa.or.jp/recruit/resident-otowa-senior-sogo-pro.html
総合診療科「病院総合医フェローシップ(トレーニングコース)」
http://www.rakuwa.or.jp/recruit/resident-otowa-senior-sogo-fellow.html