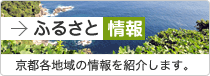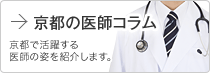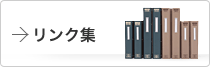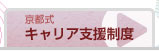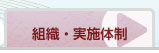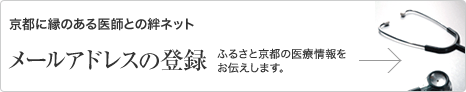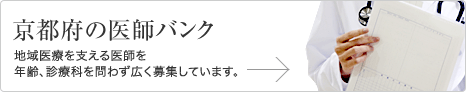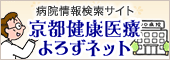京都で働きたい医師・医学生の方へ 京都で暮らし、京都で築くメディカルキャリア
KMCC(Kyoto Medical Career support Center)開設記念フォーラム
京都のスーパーGeneralists集合!
京丹後市立久美浜病院 診療部長 瀬尾 泰正先生
未来に繋げる地域医療
当院で取り組んでいる地域医療についてご紹介します。
医療は目覚ましく進歩していますが、様々な問題山積みの背景の中で地域医療崩壊が叫ばれるようになったのは皆様ご存知の事と思います。地域医療はまさに「冬の時代」と・・・。本当に地域では専門性を磨けないのか?地域医療は本当に魅力がないのでしょうか?
久美浜病院は京都北部に位置し、病床数170床で、一般110床、療養60床、診療科目は内科・外科・整形・小児科・皮膚科・歯科口腔です。田舎の弱小病院といったところでしょうか。
当院は「PCIからESDまで」を合い言葉に、内科診療は研修医を含め計6名のスタッフが携わっています。
「PCI」とは、経皮的冠動脈イ ンターベーション(※1)の略です。
虚血性心疾患、狭心症、心筋梗塞といった病態は、死に直結する病態です。いったん心筋梗塞になると、死の転帰をとるため、その治療には緊急を要します。
カテーテルを使って造影し、閉塞した血管を確認した後、ワイヤーを通しバルーン、ステントを入れて、虚血心筋を救済し心筋梗塞を改善する治療法です。
当院でのPCI成績は、症例数は多くはありませんが、待機例が少なく緊急例が多いというのが特徴かもしれません。ご高齢の方が多く厳しい病変の方も大勢いらっしゃいます。
一方「ESD」というのは内視鏡的粘膜下層切開剥離術です。
以前は胃癌も大きいものはなかなか一括切除出来なかったのですが、ESDを使うことにより、病変を一括切除し手術をしなくてすむような症例も出てきました。
当院での症例では、大部分の患者さんがなんとか一括切除し、保存的に軽快しています。
こうした治療の他に急性期脳梗塞に対する血栓溶解療法も行っています。
発症3時間以内であれば、後遺症なく治癒する可能性がある脳梗塞に対する治療法です。全く後遺症なく社会復帰することが出来た一例もあります。他にもペースメーカー、腹部エコー、心臓エコー、大腸の治療、ERC(※2)等々の検査・治療をしています。
私の「病院での一日の流れ」をご紹介します。
午前中は、エコー、胃カメラ、心臓エコーを行います。
午後は予約の診察をした後、骨髄穿刺(※3)、胸水穿刺(※4)、下部消化管内視鏡やカテ―テル検査等を行います。
緊急の止血例やカテ(※5)が入ることもあります。
久美浜病院では、医師、看護師ともに「心カテスタッフ」「内視鏡スタッフ」を同じスタッフがおこなっているのが特徴です。
ここで、久美浜病院の内科を訪れた地元の方々400人のアンケート結果をご紹介します。
―あなたが最も期待する医療は何ですか?
回答は、「いつでも利用できる医療」「一般的な医療」「自分にあった医療」と答えた方々が多く、「最先端の医療」「臓器ごとの医療」と答えた人は意外に少数でした。
これらは「地域で実践できる医療」であり、あるいは「地域で行っていかなければならない医療」という言い方も出来るかと思います。
心血管疾患や脳卒中というのは緊急での対応が迫られたり、予防やリハビリといった問題も絡みます。悪性腫瘍に関しては近年化学療法が行われたり、終末期の問題等が絡んできます。こうした疾患を「地域で診る」ということが重要なのではないかと私達は考えています。
アンケート結果に戻ります。
―重大な疾患が見つかったらどうしますか?
「久美浜病院で診てもらって、無理なら他の病院」と答えた人が72%、
「どんな病気でも最後まで久美浜病院」との回答が実に16%で、約9割の方々から「久美浜病院で診てほしい」との回答を頂きました。
地域医療にあるものは一体何でしょうか?「信頼」「期待」「責任」そして圧倒的な「存在感」であります。「プライマリ・ケア」という言葉があります。「プライマリ」とは「初期」「近接」「常在」といった意味ですが、「プリマ」「主役」という意味も含んでいます。医師は、患者さんの「全てお任せします!」という信頼の声や、医療を行った人が1人でも「ありがとう!」と言ってくれる感謝の言葉で頑張れる。そこに医療の基本があるのではないか・・・「地域医療を行う」ということは「身近で大切な人に医療を行っていく」ということです。そこには限りないプレッシャーがあります。しかしそこに「やりがい」があります。そして達成した時の喜びは計り知れません。私達が目指しているのは「切れ目のない医療」と「繋げる医療」です。人に切れ目がないように医療にも切れ目はありません。人は切り離すことのできない時間を社会生活の中で生きています。私達はその命を家族や地域にそして未来に繋げていかなければなりません。
そこで4つの課題をあげてみました。
Ⅰ. 地域にいると技術や知識が身に付けられないのでは?私達内科の医師6名は、各自得意分野、専門領域というものを持っています。「消化器領域」「循環器」「呼吸器」、麻酔のできる内科医を目指す医師もいます。当院で形成外科を目指し頑張っている研修医の先生は、研修修了時には『形成外科のできる内科医』となり、人々に頼りにされる医師として、医療に貢献していくことでしょう。
Ⅱ. 一見違う領域に思えるような手技に、共通するものがあるのでは?
上部下部内視鏡等の、「内視鏡を使う手技」には共通するものがあります。経食道エコーでは、その挿入手技に内視鏡手技が使われます。
超音波で、腹部、 心臓、血管内も診ることが出来き、カテーテルで写すのは心臓のみならず腹部の血管、下肢も写すことが出来ます。また、ポートやペースメーカー等は同様の埋め込み手技を使います。
胃瘻も気切も、瘻孔を作成する手技にも共通したものがあります。ピッグテールカテーテルは、胆嚢、胆管、血管の中にも使うこともあります。穿刺・ドレナージの時に使うことも勿論あります。下肢血管形成術に使うステントは、胆管ステントが応用されたものだと言われています。風船やステント治療にも共通した手技があります。
そして、消化管、血管といった管を操るような治療にも共通したものがあるのではないか?と私達内科医は考えています。
Ⅲ. 最新の医療知識の取得は?
私達久美浜病院の医師は、様々な研究会に参加し、知識を得ています。
研究会では、知識だけでなく多くの病院との信頼関係を得ることが出来、久美浜病院のバックアップや相談の窓口になって頂くことで、当院の患者さんに充分な医療提供を行っています。
この信頼関係のなかで気付くことは、「医療連携」というよりは「人と人との繋がり」の大切さです。京都府立医科大学附属病院 輸血・細胞医療、臨床検査部 部長の稲葉 亨先生には血液内科の領域でお世話になっていますし、市立福知山市民病院 病院長の香川 惠三先生には消化器領域で、また同総合内科の川島 篤志先生とは救急の研究会等でご一緒したりと、「人と人との繋がりの連携」が何よりも大事だと感じています。
― Change(変化)することに、Challenge
(挑戦)し続ける!
私達は新しい医療をできるだけ取り入れるように工夫してきました。新しい医療は侵襲や苦痛のない医療という形で進化しています。新しい医療を取り入れることは、医療スタッフのモチベーションアップに繋がると思います。ただし、モチベーションの源は地域における「期待」や「信頼」そして「責任」であることは言うまでもありません。
Ⅳ. 「救急は断らない!」
これは久美浜病院のスタンスであります。
平成22年6月、久美浜高校の体育祭で熱中症患者が多数発生し、久美浜病院は、なかば野戦病院と化しましたが、病院スタッフ全員で専門や診療科の垣根を超え救急治療にあたりました。
―もしあなたが急病になったらどうしますか?
という質問には、「久美浜病院で診てほしい」という回答が84%でした。
「ヘリコプターがなかったら救急が診れない」そんな地域にしてはいけないと私達は考えています。地域の救急は地域で診る、地域への信頼はここから始まると考えています。医師不足や救急たらい回しが社会問題となる時代だからこそ、必要なことだと思います。
そして「救急」は地域と私達を繋ぐ言葉になりました。
「命の授業」
近年、AEDや心肺蘇生法が一般市民にも普及しました。
私達は地元の小学校で「命の授業」を行いました。子供達にそれぞれ聴診器を渡し、実際に心臓の鼓動を聞いてもらいました。「私も生きている、あなたも生きている・・・」そんなことを実感してもらい、困った人や倒れている人に遭遇した時に、「一歩踏み出す勇気」を持ってもらいたい・・・そんな思いで開催しました。子供達も一生懸命取り組み、「命の大切さ」を学びました。命を大切にする子供達が優しい豊かな地域を築きます。そしてこういった地域では健全な地域医療が出来るというふうに考えています。
「夏だ!集まれ!久美浜キッズドクター・キッズナース」
平成23年の夏には、「夏だ!集まれ!久美浜キッズドクター・キッズナース」というイベントを開催しました。
このイベントの意図は、気長な話ではありますが「地域に根差したドクターやナースの育成」です。子供達には夏休みの宿題の課題として参加してもらいました。
「診察の準備」ということで、聴診器を使ったり、血圧、脈、体温を測ったり、病院探検や、最後には実際の診療に挑戦してもらうといった内容です。子供達は目を輝かせ、一生懸命に勉強していました。診療体験や「命の不思議」に非常に「感じる」ところがあったようでした。イベント開催にあたっては病院全体で協力し、子供たちの体験をフォローしました。
私達は子供達に「夢の扉」を開きます。子供達は私達に「夢」を与えます。20年後の未来の彼等、彼女達が成長し久美浜や地域の医療を支えてくれる・・・そんな希望を私達は持っています。地域医療の課題を克服するために最も必要なことは、私達の医療を理解する地域の人達、そしてその医療を未来へ伝えていく人達を作ることです。そして何よりも共に同じ意志を持つ「仲間」が大切であることは言うまでもありません。
「総合医」と「専門医」
皆様ご存知のように今や専門医志向で、医学辞書のように「専門医」が並んでいます。「病気が治せても、病人は治せない。」そんな専門医達が増えていると言われています。迫りくる高齢化社会、専門細分化される臓器別医療、地域医療崩壊、そんな中で「総合医」のあり方も問われる時代になったのではないか考えています。
私の考える「専門医」とは、『一人の患者さんを、 「その専門領域の疾患について」初期診療から診断治療、その後の社会生活に至るまで、その優先順位に配慮し、最善、最良の医療へと導く』いうものであると思います。特殊な知識や技術を持ち合わせているだけでは「専門医」とは言えないのではないかと考えています。「総合的な視点を持ちながら最良の医療へ導いて行く・・・」そういうことが重要だと思います。
一方、「総合医」とはなんでしょうか?
『一人の患者さんを 「全人的」に初期診療から診断治療、その後の社会生活に至るまで、優先順位に配慮して最善、最良の医療へと導く』というものであります。 「専門領域の疾患について」と 「全人的」の部分以外は同じなのです!
「総合医」もまた専門性、得意分野を持つことが重要なのではないでしょうか。
自治医大の先輩で、今年から佐賀医大の地域医療学教室の教授なられた杉岡先生という方がいらっしゃいます。杉岡先生も「専門性を持った総合医」「総合的な視点を持った専門医」の育成が必要だとおっしゃっておられました。
まとめ
地域医療とは、「都会」「田舎」のくくりではなく、あらゆる地域にそれぞれの地域医療があります。大事なことは地域の声に耳を傾けながら、「地域医療」「地域連携」の元で「切れ目のない医療」そして「未来に繋がる医療」を目指して行くことだと考えます。
専門細分化されていく医療の中で、「地域で学ぶ総合医療」には大切な何かがあるのではないでしょうか?
冬来たりなば春遠からじ・・・
地域医療の「冬の時代」が終わり、やがて「春」が訪れることを願ってやみません・・・。

(※1)経皮的冠動脈インターベーション・・・経皮的冠動脈形成術PCI(Percutaneous Coronary Intervention)PTCA(percutaneous transluminal coronary angioplasty)。アテローム等により狭窄した心臓の冠状動脈を拡張し、血流の増加をはかる治療法で虚血性心疾患に対して行われる。文章に戻る
(※2)ERC・・・内視鏡的逆行性胆道膵管造影 内視鏡検査・治療の一つ 文章に戻る
(※3)骨髄穿刺・・・主に白血病診断のため、骨髄を穿刺して血液を採取し、造血能力や血液の成熟度、異常細胞の有無などをみる検査。また、白血病の治療中にその経過を観察し、治療効果の確認に役立つ。 さらに白血病だけでなく、再生不良性貧血、溶血性貧血、悪性貧血の診断や、骨髄腫やリンパ腫、血小板減少性紫斑病などの他、各種の癌が骨髄へ転移しているかどうかを調べる際にも有用。 文章に戻る
(※4)胸水穿刺・・・異常な胸水の有無は、胸部X線検査や胸部CT検査でもわかるが、胸水の一部を採取して調べることで障害の様子や原因を調べることが出来る。胸水には、炎症がある時に病巣から出る滲出液と、毛細血管などから漏れ出る漏出液の2種類があり、胸水が異常に増加すると、呼吸困難、胸痛、胸部圧迫感、咳、頻脈、発熱等の症状が現れる。文章に戻る
(※5)カテ・・・カテーテルの略称。(例)心臓カテーテル検査⇒心カテ カテの先端⇒カテ先(かてさき)文章に戻る