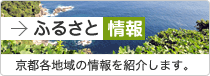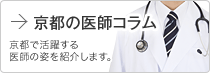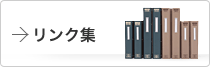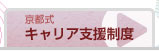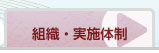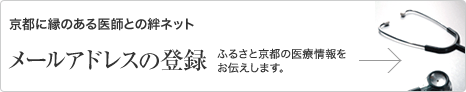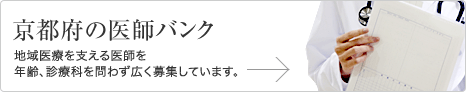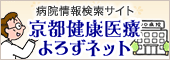京都で働きたい医師・医学生の方へ 京都で暮らし、京都で築くメディカルキャリア
KMCC(Kyoto Medical Career support Center)開設記念フォーラム
京都のスーパーGeneralists集合!
市立福知山市民病院 総合内科医長 川島 篤志先生
地域基幹病院での「総合内科」と「総合内科医の育成」
福知山市は、ある程度の都市機能を持った人口約8万人の「地域の小都市」であり、市立福知山市民病院は医療圏10万人地域にある地域基幹病院です。本日は当院での「総合内科としての臨床」「総合内科医・研修医の育成」についてお話しします。
地方の総合病院にとって大事な事のひとつは、「専門医が専門医らしく」働けること。これが一体どういう意味を持っているのか、わかる方とわからない方がいらっしゃると思いますが、この後でまたお話します。
「総合内科医が活躍できる病院」また「研修医が活き活きと働ける病院」というものを、地域基幹病院としてどのように取り組んでいくべきか探っていきたいと考えています。
個人的な意見としては、臨床経験が少ない研修医のうちは、「患者さんから学ぶ」と考えれば、何処の病院で勉強しても良いのでは?と思います。しかし、研修医の視点では『自分の「医療の質が担保」されること、教育により成長が実感できる環境』つまり、「安全」で「教育的な環境」が大事だと思います。実際、国内の臨床研修で有名な病院の中にはかなり都会から離れた病院もあるのは、「地方の魅力ある病院」が存在している証明ではないでしょうか。
どの基幹病院に於いても、医者としてやるべき仕事があります。外来、検査・手術、入院、救急、そして他の病院雑務です。
通常、臓器別専門医であっても、自身の得意分野(検査・手術、専門領域の入院処置等)以外の病院業務があります。例えば新患対応、入院時にどの臓器に属するか判らない患者さんへの対応もありますし、勿論当直もあります。また病院内の委員会、事務的作業等をこなさなければなりません。医師不足の病院に於いて、知らず知らず医師の負担になる病院業務がある現実は、あまりメディアでも取り上げられない部分です。京都府福知山市も医師不足ですからこういった事情は以前にはありました。
そういった事情に対して市立福知山市民病院の総合内科が、どのように活躍出来るのかは、当院ホームページに掲載していますので一度ご覧下さい。
※市立福知山市民病院HP
病院トップページから>各科・部門の紹介>総合内科 をクリックして下さい。
http://www.fukuchiyama-hosp.jp/
総合内科の得意分野
総合内科では、やはり「診断学」は大きな得意分野です。地域基幹病院での診療分野としては、感染症診療(もしくは発熱診療)や多臓器に渡る複数科の疾患、また特定の専門医が病院に在籍していない領域を、誰が診るかで質が変わってくると思います。「個別の臓器別専門医がそれぞれに診療」するのか、「総合内科としてチームで診療」するのかで、医療の質が変わることは想像に難くないと思います。
地域基幹病院には、上記のような大学に無いフィールドが数多くあります。このフィールドの「質」をいかにして高めるかが大切です。「診断学が発揮できる場」として新患外来、救急外来がありますが、ここで必要となるのが、「病歴」「身体診察」そしてそこから想定される「鑑別診断」が重要になります。これは言わずもがな、「臨床の基本中の基本」です。
臓器別専門医は、特異度の高い検査を主体とした疾患の判別は得意かもしれません。しかし、医師として「広く診る」という点に関しての基本的姿勢は「総合内科」の方が幅が広い可能性があります。また「新患外来」
「救急外来」は実は地域の診療所の先生からの窓口でもあり、「病院内での存在感」だけでなく「地域にとっての存在感」というものが求められていると思っています。
「診断学」で適切に診断をしていくと、過去にその地域に無かった症例が表面化されてきます。当院でいえば「感染症」「炎症性疾患」、あと専門領域の常勤医がいなかった疾患です。私が福知山に赴任して3年が経ちますが、以前は当院に欠けていた分野に対して、適切に疾患を判断し、治療、検査に結び付けてこれたのではと感じています。
そして診断した疾患のアウトプットも病院にとって大切です。まだ学会での発表や論文化は追いついていませんが、『日本一受けたい授業はここにある』という文面が掲示されている若手医師向けの広告の中に、日本中の有名な病院の中に混じって福知山市民病院が掲載されました。始めは「なんかの間違いじゃないのかな~」と思いましたが、自らアウトプットしていた結果が、こんな風に捉えられるのか・・・と感慨深いです。
教育を受けたいのは誰か?
それは研修医や若手医師です。行政や住民は、つい即戦力を求めるきらいがありますが、研修医の存在は地域基幹病院にとって非常に大切です。研修医がなぜ重要かというと、「救急」や「入院」をしっかり診ようとします。「体力の続く限り診る」という意味ではなく、臨床経験が浅い分、そして自分自身の為に「一生懸命」診療にあたります。実際高い能力があるかと言うと、必ずしもそうではないので、病院が「質の担保」をし、研修医の「バックアップ」になることが大切です。優秀な指導医と一緒、もしくは「チームで診る」ことにより、「教育的」且つ「安全」な環境があれば、教育を受けたいと思う数多くの研修医は、一緒に働いてくれます。また中には、5年後10年後に地域へ戻ってくる将来のスタッフ候補に成り得る研修医もいるはずです。適切な医療を行うには人材が必要です。「教育」のあるところに「人」が集まると考えています。つまり、いい医療を行うには、教育が必要というわけです。
教育とは何か?
普通の教育をする
毎朝ベッドサイドに行って回診をし、昼間にカンファレンス、夕方にチェックをする。
このごく当たり前のことが日本ではまだ出来ていない病院が多く、実際には当たり前のことが出来ている病院に医師が集まっています。
福知山市民病院の研修医には、医学生時代に当院で勉強したことがあり、それがきっかけで現在当院で研修中の医師もおります。
医学生に、実際に病院を見てもらい病院の良さを知ってもらうのもよいでしょう。将来、内科系に進む医師でなくとも、また何かの機会に戻って来る、もしくは病院の評判が高ければ、口コミで医師が集まるのではないでしょうか。
医師育成には、労力が掛かりますが、「質」を高めるためには必須だと思っています。
みんなで勉強会
「内科カンファレンス」、「内科と外科の手術に関するカンファレンス」は当院を含め何処の病院でも以前から行っているのではないかと思います。当院では、それ以外に「救急に関するカンファレンス」「症例検討」、もしくは「出版物を読むカンファレンス」などを行っています。勉強会は若手医師だけで読むより、ちょっとした上級医スパイスの効いたカンファレンスにすることにより「質」が向上します。「症例検討」も、研修医を含め多人数で行います。
また時々は、院外の先生を招聘し、若手医師が本当の「スタンダード」を学ぶ機会を作っています。若手医師に「エキスパートオピニオン」だけではなく「グローバルスタンダード」が大切であると伝える事が出来るととも、院内教育の必要性を再確認出来ます。
今迄に、福井大学医学部 総合診療部 林 寛之先生、藤田保健衛生大学 総合救急内科 山中 克郎 先生など、年間3~4人の先生にご来福頂きました。また院内での講演会の利点は、複数人で聞くことが出来ることです。ある1人の医師が勉強会に行くと、医師1人の知識にしかなりませんが、院内講演会は十数人の研修医・若手医師が同時に、ときに数十人の多職種のスタッフが同時に同じ話を聴くことによって、病院内に同じ文化を育むことが出来ると思います。
これを病院予算でしていただいているのが、当院の教育にかける意識の高さを表しているともいえます。
また院外講師だけではなく、「自分達でなんとかしよう!」と思っています。「救急のチェックリスト大会」「感染症勉強会」というような勉強会は、院内でのアイデア次第で創りあげてきています。
当然、人前で話すためには自分が勉強することが必要です。人のために話すことで、自分自身勉強が出来、知識が増える。当院ではこの好循環が出来ています。医師に対する勉強だけではなく、看護師を含めた勉強会も開催しています。例えば、「医療安全」という観点から、CVCという中心静脈カテーテルの安全な処置方法の勉強会を開催するなど、病院と患者さまにとって大切なことを病院スタッフ全員で勉強し、意志統一を図っています。
当院の様々な試みで、病院見学をはじめ、スタッフとして実際に勤務する医師、医学生が、この短期間でぐっと増えてきています。2008年医師52名だったのが、現在70名です。医師が増えることは、病院の経営面にも好影響を与えます。
マグネットホスピタル
現在(2011年度)当院総合内科には、専攻医4名を含め8名のスタッフがおります。この8名で内科の新患外来、救急外来等「診断学」が発揮出来るところの診察をし、総合内科としての得意診療領域や、他の専門内科の非専門領域であっても「総合内科」で担っています。常に約60名程の患者さんを診ていますが、この60名という数字は、当院の病床数急性期250床、内科約150床から見ると、かなりの数を占めているとご理解いただけるかと思います。
北近畿地域で、総合内科領域に8名の医師がいることは贅沢な環境かもしれませんが、まだまだ「総合内科医」が必要です。今後「総合内科医」を目指す医師が増えることを願うとともに、また病院側も「総合内科医の育成」に取り組んでいきたいと思います。
病院の「教育」を充実させると、若手、中堅の「医師を育てる教育がしたい医師」が集まって来ます。「教育」という「資源」で「マンパワー」が集まってくる「マグネットホスピタル」になることが当院の将来的なビジョンです。
三者バランス~専門医が専門医らしく働ける
では実際に、「総合内科医」の存在が「臓器別専門医」の負担軽減に成り得るのでしょうか?
当院に在籍履歴のある専門医にアンケートをとりました。結果は「以前に比べ楽になった」「仕事量が変わった」との回答を頂きました。 専門医が専門医らしく医療を行うことは、地域の医療の質を向上させます。当院循環器科の医師は、「循環器医師が循環器医師らしいの仕事が出来ている!」と堂々と言ってくださっています。これは専門医をカバー出来る医師の存在によって成り立つと考えています。
地域基幹病院において、「臓器別専門医」「総合内科医」「研修医」のバランス、尊重関係が重要だと思っています。ここで重要になるのは、病院トップのコントロールがあってこそ、だと思い、こういった環境で医療をさせていただいていることを感謝しています。
情報発信
「総合内科の専門性」「臓器別専門医の負担軽減」「医学教育・研修」これは当院ホームページ『総合内科の紹介』に特色として掲載されている言葉です。また 「教育力のない病院には未来はない!」これは当院香川病院長が常々口にされている言葉です。香川病院長の理念の元で医療と教育に携われることを誇りに思います。総合内科が病院の中で「教育のエンジン」として存在することで、多くの医師がまた更に集まってくる。このシステムを持つ病院こそが、今後の地域の医療を支えることが出来るのではないでしょうか。
私川島は「総合内科/臨床研修について」というブログをしています。病院内外のイベントに関することや、感じたことを情報発信しています。このブログを読んだ多くの人と「教育」というキーワードで繋がっていきたいと考えています。
「総合内科/臨床研修について」のブログ http://fukugim.blogspot.com/